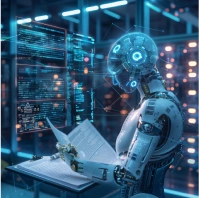インサイドセールスに失敗する原因10選!事例と成功のポイントも紹介

電話やオンラインツールを使用して、非対面で行うインサイドセールス。顧客先を訪問しない内勤型営業は、営業コストを削減しながらアプローチ数を増やせるのが特徴です。
しかしインサイドセールスには、組織改革や専門性の高いスキルを持つ人材の確保が必要なため、導入しても失敗するケースは少なくありません。
そこで本記事では、インサイドセールスに失敗する原因について解説します。事例と成功のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
インサイドセールスで失敗する原因10選と解決策

では早速、インサイドセールスで失敗する原因10選と、解決策について解説します。
- 目的が曖昧なまま導入してしまった
- インサイドセールスの目的がテレアポになっている
- 適切なKPIを設定できていない
- 各部門間の連携が取れていない
- 顧客に適切なタイミングでアプローチできていない
- そもそもリードを獲得できていない
- 人手不足により営業力が低下している
- マネジメント力が低い
- 教育体制が整備されていない
- ツールを活用できていない
目的が曖昧なまま導入してしまった
インサイドセールスを導入する目的は、企業によって異なるものの、ゴールをイメージできなければ営業活動を最大化できません。
結果的に成果につながらず、チームのモチベーションが低下すれば、生産性の低下を招きます。
インサイドセールスは、導入する目的と役割を明確にすることが解決への糸口です。
目的が明確ならゴールをイメージしやすくなり、スタッフの役割を理解して共通認識を持てば、営業活動を最大化できるでしょう。
インサイドセールスの目的がテレアポになっている
インサイドセールスの目的や役割を正しく理解できておらず、テレアポ部隊になる失敗事例も多くあります。
インサイドセールスにはさまざまな手法がありますが、テレアポもその一つです。
ただし、通常のテレアポとインサイドセールスにおけるテレアポでは、目的が異なります。
通常のテレアポは、アポイントの獲得が目的です。一方インサイドセールスでは、見込み顧客との関係性を構築しながら、商談の機会を創出するのが目的です。
通常のテレアポは、顧客との関係性構築を目的としていないため、一度断られたら次の架電に進みます。
インサイドセールスでのテレアポは、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)を目的にしているので、中長期的に顧客との関係性を構築するのが大きな違いです。
インサイドセールスにおける、テレアポの目的と役割を明確にしてチームで共有すれば、テレアポ部隊になるのを回避できるでしょう。
適切なKPIを設定できていない
KPIを適切に設定できていないのも、失敗の原因です。
そもそもKPI(重要業績評価指標)は、KGI(重要目標達成指標)までの中間指標を設定することであり、ゴールまでのプロセスを見える化する目的があります。
たとえば、インサイドセールスのKPIでは、「架電数や通話時間」「メール開封率」などの項目を設定します。
適切なKPIを設定できていなければ、ノルマ達成が目的となり応対品質が低下するだけでなく、本来の目的を見失いゴールにたどり着けない恐れがあります。
目標を高く設定しすぎてしまうと、達成できなかった場合にモチベーションの低下や現場の混乱を招きかねません。
KPIは自社の現状を踏まえて、達成しやすい現実的な数値や数量であることも重要です。KGIから逆算して、適切なKPIを設定しましょう。
各部門間の連携が取れていない
部門間の連携が取れずに失敗する事例もあります。
インサイドセールスは、分業制で行うため部門間の連携が取れていないと、認識のズレが生じて業務に支障を与える恐れがあります。
誤った情報を引き継げば、業務を最適化できずに失注のリスクを高めかねません。顧客を納得させる提案ができなければ、信頼してもらえず企業のイメージを低下させる恐れもあります。
こうした失敗を防ぐには、「社内の連携体制を整備すること」と「各部門の役割を明確にすること」が必要不可欠です。
顧客に適切なタイミングでアプローチできていない
アプローチのタイミングを見誤るという失敗も多くあります。
たとえば、自社Webサイトから資料請求や問い合わせをする顧客は、自社商材への関心や興味が高いと考えられるでしょう。
見込み顧客からのアプローチという機会を得ても、対応が遅れると競合他社に乗り換えられる恐れがあります。
解決策は、リードナーチャリングを徹底して、購買意欲が高まったタイミングを見極めることです。最適なタイミングを見逃さないためにも、迅速な対応を心がけてください。
そもそもリードを獲得できていない
そもそも、リードを獲得できなければ商談の機会を創出できません。
インサイドセールスには、BDR(新規開拓型)とSDR(反響型)という2つの種類があります。
BDRは、電話やメールなどを活用して、企業から見込み顧客にアプローチする「アウトバウンド型」の営業手法です。
SDRは、資料請求や問い合わせがあった見込み顧客に対応する、「インバウンド型」の営業手法という違いがあります。加えて、SDRは既存顧客へのフォローアップにも適しています。
どちらか一方の手法だけでは、成果につながりにくいケースもあります。BDRとSDRをバランスよく組み合わせることが重要です。
人手不足により営業力が低下している
人手不足により営業力が低下すると、営業活動を最大化できません。
このケースでは人材の確保が最優先事項ですが、少子高齢化の影響から、業界全体が人手不足の課題を抱えています。
人材の確保が難しいなら、インサイドセールスの外注を検討してください。
ノウハウを持つプロが対応するので、営業活動を最大化できます。即戦力になるスタッフを確保できるため、成果につながりやすくなるのもメリットです。
マネジメント力が低い
マネジメント力が低いために、インサイドセールスに失敗するケースもあります。
インサイドセールスにおけるマネジメント力は、スタッフと管理者それぞれに必要です。
インサイドセールス部門では、マーケティング業務やクロージングやフォローアップまで、対応領域が多岐にわたることも少なくありません。業務量が多く煩雑化しやすい場合は、スタッフのセルフマネジメント力が求められます。
管理者は、チームの営業力が低下しないように、組織全体を俯瞰しながら管理しなければなりません。
いずれの場合も、マネジメント力が低ければスムーズに業務を遂行できないでしょう。
そこで、マネジメント力の高い人材を確保すれば問題を解決できます。
教育体制が整備されていない
インサイドセールスには、専門性の高いスキルや知識が求められます。
社内の教育体制が整備されていなければ、インサイドセールスの成功に必要な人材は育ちません。
解決策としては、研修を導入する方法と、ツールやロールプレイングなどを用いて社内で対応する方法があります。
教育体制を整備できればノウハウも蓄積されるので、営業力の向上につながるのもメリットです。
なお、こちらの記事では、インサイドセールスの人材育成について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
インサイドセールスの人材育成ガイド!重要性や研修方法・必要なスキルを紹介
ツールを活用できていない
ツールを活用できていないのも、インサイドセールスではよくある失敗例です。
インサイドセールスには、MA(マーケティングオートメーション)や、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)などさまざまなツールを活用します。
ツールの種類によって搭載されている機能が異なるため、目的にマッチしているツールを選定することも重要です。
目的にマッチしたツールを選んでも、使いこなせなければ意味がありません。ITリテラシーの高い人材の確保も必要です。
こちらの記事では、インサイドセールスツールのおすすめや選び方を紹介していますので、あわせて参考にしてください。
インサイドセールスツールのおすすめ20選を徹底比較!選び方やメリットも紹介
インサイドセールスの失敗から学ぶ成功のポイント

続いて、インサイドセールスの失敗から学ぶ、成功のポイントを5つ紹介します。
- インサイドセールスの目的を明確にする
- 社内での理解を得てから体制を整備する
- 情報共有できる体制を整備する
- 社内ノウハウを蓄積する
- 内製化が難しいなら外注を検討する
インサイドセールスの目的を明確にする
インサイドセールスの目的が不明瞭なまま導入しても、スタッフが理解できていなければ業務品質が低下する恐れがあります。営業力が低下して成果を出せなければ、売上の低迷を招きかねません。
なぜインサイドセールスを導入するのかを明確にして、社内で共有してください。
目的が明確になれば各部門の役割も決まるので、チームのモチベーションアップにもつながるでしょう。
社内での理解を得てから体制を整備する
インサイドセールスの導入には組織改革が必要なため、社内での理解が得られているかが重要です。
スタッフによっては部署異動を強いられることもあるため、社内での理解を得られないまま導入すると現場が混乱する恐れがあります。
まず、社内での理解を得ることが先決です。理解を得られたら次に体制を整備しますが、体制が整うまでには時間がかかることに留意しましょう。
スモールから始めて、徐々に改革を進めることも大切です。
情報共有できる体制を整備する
そして、情報共有できる体制の整備も欠かせません。
情報共有にはツールが役立ちますが、定例会や1on1ミーティングなども有効です。
特に、テレワークを導入している企業では、コミュニケーション不足から情報をスムーズに共有できないケースがあります。
クラウド型のツールを導入すれば、テレワークで働くスタッフとのコミュニケーションも強化できます。
社内ノウハウを蓄積する
社内ノウハウを蓄積すれば、教育やマニュアルに活かせます。
そこで、PDCAサイクルを回しながら効果検証と改善を繰り返せば、ノウハウを蓄積できます。
なお、PDCAサイクルのスパンが長いと、課題の発見が遅れるので、日次や週次などできるだけ短いスパンで回すのも成功のポイントです。
内製化が難しいなら外注を検討する
人手不足やノウハウ不足などの課題があると、インサイドセールスを導入できないケースもあります。
内製化が難しい場合は、外注を検討してください。将来的に内製化を目標としている場合は、短期間だけ外注するのも選択肢の一つです。
ただし、ノウハウを共有してもらえなければ、契約解除後に内製化を実現できません。依頼する場合は、代行会社がノウハウを共有してくれるかを確認してください。
インサイドセールスで失敗を避けるならディグロス

インサイドセールスで失敗を避けたいなら、株式会社ディグロスにお任せください。
弊社では、成果報酬型でお客様のご要望に沿った商談の場をセッティングします。
これまで1,600社の支援と、年間3,400以上のプロジェクトに携わった実績がございます。
電話やメールでご説明いたしますので、インサイドセールス代行をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ:インサイドセールスの失敗から学び成功に活かそう

インサイドセールスの導入には組織改革や、専門性の高いスキルを持つ人材の確保が必要不可欠です。
目的が曖昧なままではやるべきことを把握できないため、インサイドセールスに失敗する事例は少なくありません。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、インサイドセールスの失敗から学んで成功に活かしてください。