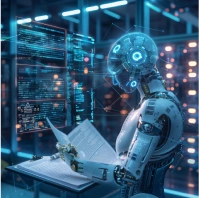インサイドセールスの内製化を成功させる8ステップ!外注との違いも比較

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、対面式の営業活動が制限されたことを受け、多くの企業でインサイドセールスの導入が進んでいます。
しかし、インサイドセールスの立ち上げには組織改革が必要なことから、内製化しても期待どおりの成果が出ないケースは少なくありません。
そこで、本記事では、インサイドセールスの内製化を成功させる8ステップを紹介します。内製化と外注化の違いについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
インサイドセールスの内製化とは?

インサイドセールスの内製化とは、チームの立ち上げから運用までを、すべて自社リソースで実施することです。
社内体制の整備には、大掛かりな組織改革が必要になるケースもありますが、内製化すれば柔軟に対応が可能になるのはメリットです。
また、蓄積される営業ノウハウは、企業の長期的な資産になります。
インサイドセールスの内製化が注目される理由

では次に、インサイドセールスの内製化が注目される3つの理由を紹介します。
- 多様化する顧客ニーズに対応できる
- 柔軟な働き方に対応できる
- 人手不足の課題を解消できる
多様化する顧客ニーズに対応できる
近年、インターネットの普及やデジタル化の加速により、市場動向や消費者ニーズは多様化しています。
こうした変化に対応できなければ、企業としての成長は見込めません。
そこで、インサイドセールスを内製化すれば、蓄積された社内ノウハウを活用して、多様化する顧客ニーズにも柔軟に対応できます。
柔軟な働き方に対応できる
多様化は顧客ニーズに限らず、働き方にも求められます。
2019年に施行された「働き方改革」の影響を受け、柔軟な働き方への対応という従業員ニーズも高まる傾向にあります。
そこでインサイドセールスを内製化すれば、リモートワークやフレックスタイムに対応できるようになるのはメリットといえるでしょう。
人手不足の課題を解消できる
そして、近年多くの企業が抱える人手不足の課題を解消できるのもメリットです。
インサイドセールスは、内勤型営業とも呼ばれるように、顧客先に出向く必要がありません。電話やメール、ITツールなどを使用しながら非対面で実施するので、限られたリソースでも対応できます。
また、移動時間を顧客対応に充てられるようになり、地理的な制約もないため全国に向けてアプローチできるのもメリットです。
インサイドセールスの内製化により、自社スタッフのスキルがアップすれば、組織力の強化にもつながるでしょう。
インサイドセールスを内製化する4つのメリット

それでは、インサイドセールスを内製化するメリットを4つ紹介します。
- 自社ノウハウや営業資産を蓄積できる
- PDCAを素早く回せる
- フィードバックをスムーズに開発や改善に反映できる
- 情報漏洩のリスクを軽減できる
自社ノウハウや営業資産を蓄積できる
インサイドセールスを内製化する最大のメリットは、自社ノウハウや営業資産を蓄積できることです。
たとえば、テレアポで商談の機会を獲得しても、商談で顧客を納得させる提案ができなければ成果にはつながりません。
顧客を納得させるには、課題やニーズの把握、自社商材への深い理解が不可欠です。
インサイドセールスを内製化すれば、実務を通して課題やニーズ、自社商材への理解が深まります。蓄積された自社ノウハウは、結果的に営業資産になります。
PDCAを素早く回せる
そして、PDCAサイクルを素早く回せるのもメリットです。
すべて自社リソースで対応すれば、効果検証や改善のPDCAサイクルを短いスパンで回せます。
インサイドセールスを外注すると、思いどおりにPDCAサイクルを回せなくなり、課題の発見と改善が遅れる恐れがあります。
そこで、インサイドセールスを内製化すると、自社のタイミングでPDCAサイクルを回せるようになり、営業活動の最大化にもつながるでしょう。
フィードバックをスムーズに開発や改善に反映できる
インサイドセールスを内製化すると、顧客からダイレクトにフィードバックを受けられます。
顧客の意見や要望は、ニーズや市場動向の把握に不可欠です。新鮮なフィードバックを開発や改善に反映することで、自社商材の価値が高まり市場での優位性を確立できます。
顧客ニーズに対して的確に対応できるようになれば、顧客満足度の向上やブランディングなども期待できます。
情報漏洩のリスクを軽減できる
インサイドセールスの内製化は、顧客情報や機密事項などを自社で管理するため、情報漏洩のリスクを軽減できます。
外注する場合は、どこまで情報を開示するかを決めて、進捗状況なども都度確認が必要です。
こうした手間を省ければ、業務負担も軽減されるでしょう。
インサイドセールスを内製化する3つのデメリット

インサイドセールスの内製化には、デメリットも存在します。
- 人材採用や育成にコストがかかる
- 設備投資が必要になる
- 成果が出るまでに時間がかかる
以降で3つのデメリットを紹介しますので、理解したうえで導入してください。
人材採用や育成にコストがかかる
インサイドセールスは、非対面で行うため、担当者には専門性の高いスキルや知識が求められます。
対面での営業経験が豊富だからといって、インサイドセールスでも同様の成果を出せるとは限りません。
また、専門性の高いスキルや知識を持つ人材の採用は非常に困難な傾向にあるため、確保するには高待遇の条件を用意することが不可欠です。
経験やスキルに乏しい人材の場合は、育成コストもかかるでしょう。
設備投資が必要になる
インサイドセールスの立ち上げには、組織改革や設備投資が必要になるのも留意点です。
| 設備 | 分業体制の整備 通信環境の整備 セキュリティソフトなど |
|---|---|
| ツール | MA(マーケティングオートメーション) SFA(営業支援システム) CRM(顧客関係管理) 名刺管理ツール Web会議ツールなど |
上記はあくまでも一例であり、必要な設備は企業によって異なります。
インサイドセールスは分業を前提としているため、分業体制の整備は不可欠です。
電話やメール、Web会議ツールなどを使うための通信環境も整備しなければなりません。
ソフトやツールを使う場合は、専門的な知識を持つ人材の確保が必要な場合もあります。
また、企業によっては組織改革によって、これまでとは働く環境が大きく異なるスタッフもいます。インサイドセールスの導入に当たっては、社内の理解を得ておくことも大切です。
成果が出るまでに時間がかかる
インサイドセールスを内製化したからといって、すぐに成果が出るわけではありません。
特に立ち上げ直後は、社内ノウハウが蓄積されていないため、思いどおりに行かないこともあります。
インサイドセールスを内製化するなら、長期的な視点で取り組むことが大切です。
インサイドセールスの内製化を成功させる手順8ステップ

では次に、インサイドセールスの内製化を成功させる手順を8つのステップに分けて紹介します。
- 導入目的を明確にする
- 取り扱う商材を決める
- 営業手法を決定する
- 分業体制を確立する
- シナリオを作成する
- KPIを設定する
- 教育体制を整備する
- システムやツールを導入する
ステップ1.導入目的を明確にする
まず、なぜインサイドセールスを導入するのか、その目的を明確にしてください。
目的が不明瞭なまま戦略を立案しても、成果にはつながらないでしょう。
目的を明確にするには、現状の課題を洗い出し、改善に必要な施策を整理します。
インサイドセールスの内製化を成功させるには、導入目的を明確にして社内で共有することが大切です。
ステップ2.取り扱う商材を決める
次に、取り扱う商材を決めます。
複数の商材を扱っている場合は、最も自社の強みを活かせる商材に絞るのもポイントです。
立ち上げ直後はノウハウに乏しいため、すべての商材を扱うのは現実的ではありません。無理に進めて現場が混乱すれば、チームのモチベーションが低下します。
はじめは、自社が最も得意とする商材に絞るとよいでしょう。起動に乗りノウハウが蓄積されれば、他の商材も扱えるようになります。
ステップ3.営業手法を決定する
インサイドセールスの営業手法は、大きく2種類です。
| 手法 | 目的 | 手段 | ターゲット |
|---|---|---|---|
| BDR (アウトバウンド) | 新規顧客開拓 | テレアポやメールで企業から顧客にアプローチする | 大手企業 |
| SDR (インバウンド) | 見込み顧客の育成 | 資料請求や問い合わせがあった顧客にアプローチする | 中小企業 |
BDRは企業から顧客に能動的にアプローチするのに対して、SDRは顧客からのアクションに応じる受動的な営業手法です。
さらに、アプローチの手段やターゲットも異なるので、自社に合う手法を見極める必要があります。
ステップ4.分業体制を確立する
営業手法を決めたら、次は分業体制を確立します。
| 分業体制 | 部門分け |
|---|---|
| 分業型 | マーケティング部門 インサイドセールス部門 フィールドセールス部門 |
| 独立型 | インサイドセールス部門がすべてを担当する |
| 協業型 | 状況に応じて分業型と独立型を使い分ける |
このように、分業体制で各部門の役割や業務範囲が異なります。
特に分業型では、各部門の役割が曖昧だとスムーズに連携できません。インサイドセールスでは、部門間の連携が不可欠です。
加えて、分業体制を確立する際には、適材適所な人材配置も意識してください。
ステップ5.シナリオを設計する
トークスクリプトは、アプローチに必要な顧客との会話内容をまとめた台本です。
経験やスキルに乏しいスタッフでも、トークスクリプトを参考にすればスムーズに会話を展開できます。
とはいえ、顧客によって課題やニーズが異なるように温度感も違います。柔軟に対応するためにも、顧客の温度感に合わせて、トークスクリプトを複数用意してください。
ステップ6.KPIを設定する
次は、KPI(重要業績評価指標)を設定します。
KPIは、目標までのプロセスを数値化して、進捗状況を定量的に把握する指標です。
たとえば「今よりアポイント数を増やす」と漠然とした目標では、目標を明確にイメージできません。
「1日3件」「1週間に15件」このように数値で具体的に設定すると、目標をイメージしやすくなります。
ただし、目標が高すぎると達成できなかったときモチベーションが低下するので、現実的な目標であることも大切です。
加えて、最終目標であるKGI(重要目標達成指標)から逆算して設定すると、適切なKPIを設定できます。
ステップ7.教育体制を整備する
そして、教育体制も整備も重要な要素です。
人材を確保できても、スキルや知識に乏しければ営業活動を最大化できません。
不安を抱えたまま業務を続けても、成果を出せなければ自信が持てずモチベーションを維持できなくなります。
特にインサイドセールスは、非対面営業のため、対面営業とは異なるスキルや知識が求められます。
| 営業担当者 | 声のコミュニケーション力 ヒアリング力・傾聴力 課題解決能力 ITリテラシーなど |
|---|---|
| 管理者 | マネジメント力 リーダーシップ コミュニケーション力など |
このように、立場でも求められるスキルが異なります。
インサイドセールスの内製化をスムーズに進めるためにも、社内研修の検討が必要になるかもしれません。
ある程度スキルが身についてきたら、ロールプレイングや成功事例に基づくマニュアルの作成なども取り入れるとよいでしょう。
ステップ8.システムやツールを導入する
インサイドセールスの成功には、システムやツールの導入が不可欠です。
ツールやシステムを活用すれば、事務作業を自動化でき、業務効率化を図れます。限られたリソースでも対応できるため、人手不足の課題も解消できるでしょう。
ツールにはログが記録されるので、蓄積されたデータを活用できるのもメリットです。さらに、インサイドセールスでは非常に重要となる、情報共有もしやすくなります。
なお、こちらの記事では、インサイドセールスツールのおすすめや選び方を紹介していますので、あわせて参考にしてください。
インサイドセールスツールのおすすめ20選を徹底比較!選び方やメリットも紹介
インサイドセールスは内製化・外注どっちが良い?

インサイドセールスは外注する選択肢もありますが、企業によって向き不向きがあるので、内製化と外注のどちらが良いか迷うこともあるでしょう。
以降で内製化と外注が適している企業の特徴を紹介します。
- 内製化が適している企業
- 外注が適している企業
内製化が適している企業
内製化が適している企業の特徴を以下にまとめました。
- インサイドセールスの立ち上げ経験がある
- 社内に経験のある担当者がいる
- リソースを確保できている
- 社内体制が整備されている
これまでにインサイドセールスの立ち上げ経験があり、人材も確保できているなら、スムーズに内製化できるでしょう。
ただし、リソースに余裕があることや、新たにインサイドセールス部門を立ち上げる体制の確保は不可欠です。
自社リソースで対応できれば、導入コストを最小限におさえられるでしょう。
外注が適している企業
外注が適している企業の特徴は以下の通りです。
- インサイドセールスの立ち上げ経験がない
- 経験のある社員がいない
- リソースの確保が難しい
過去にインサイドセールスを立ち上げた経験がなく、現在対応できる人材も確保できていない場合は、外注が適しています。
外注費用はかかりますが、ノウハウを持つスタッフが対応するので、採用の手間やコストをおさえられます。結果的に売上につながれば費用対効果は高いといえるでしょう。
インサイドセールスの内製化が難しいなら外注もおすすめ

インサイドセールスの内製化を検討しているものの、現状では難しい場合は、外注でノウハウを蓄積してから内製化に切り替える方法もあります。
インサイドセールスのテレアポ代行なら、1,600社以上の支援実績を持つ株式会社ディグロスにお任せください。
成果報酬型で、お客様のご要望に沿った形のアポイントメント(商談の場)をセッティングします。
「アポイントメント獲得」と「プロデュース力」に特化しているため、業務効率化や成果の最大化を目指すお客様におすすめです。
インサイドセールスのテレアポ代行をご検討中の企業様には、電話やメールでご説明いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:インサイドセールスの導入は現状に合わせて内製化・外注を見極めよう

インサイドセールスの導入には、内製化と外注の選択肢があります。
今すぐ内製化が難しい場合は、外注でノウハウを蓄積すれば将来的に内製化にも対応できるでしょう。
それぞれにメリットとデメリットがあり、向いている企業の特徴も異なるので、現状に合わせて内製化と外注を慎重に見極めてください。