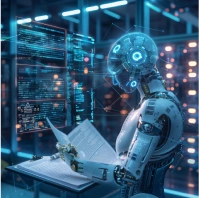インサイドセールスはやめとけと言われる8つの理由!メリットや向いている人の特徴も

インサイドセールスは、電話やメールなどを活用しながら非対面で行うため、オフィスやテレワークなど多様な働き方に対応できます。
しかし、多くのメリットがある反面「やめとけ」という意見があるのも事実です。
このような意見があると、インサイドセールスの導入を検討している企業は、不安に思うこともあるでしょう。
そこで本記事では、インサイドセールスはやめとけと言われる8つの理由と、解決策5選について解説します。企業・営業担当者それぞれに与えるメリットも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
インサイドセールスはやめとけと言われる8つの理由

では早速、インサイドセールスはやめとけと言われる8つの理由を紹介します。
- 一人あたりの対応する見込み顧客数が多い
- 担当者のモチベーション維持がしづらい
- 部門間の板挟みになりやすい
- フィールドセールスとの情報共有が難しい
- 目標が定性的でイメージしづらい
- 顧客との信頼関係を築くまでに時間がかかる
- 担当者には専門性の高いスキルや知識が求められる
- 社内からの理解が得られにくい
一人あたりの対応する見込み顧客数が多い
インサイドセールスは、顧客先に出向く必要がありません。移動にかかる時間を顧客対応に充てられますが、一人の営業担当者が対応する見込み顧客数は増えます。
また、成果につなげるには、パーソナライズされた対応が求められます。結果として、アプローチ数を増やせても、個々の担当者にかかる負担が大きくなるのは懸念点です。
担当者のモチベーション維持がしづらい
担当者のモチベーション維持がしづらいのも、やめとけと言われる要因です。
電話やメールで見込み顧客にアプローチしながら、顧客との関係性を構築するのがインサイドセールスの役割です。相手の表情や温度感を把握しづらいため、スムーズに関係性を構築できないケースは少なくありません。
加えて、ルーチンワークになりやすいことや、商談はフィールドセールスが行うため、直接的な成果を実感しづらいのもモチベーションを維持しづらい理由です。
部門間の板挟みになりやすい
そして、部門間の板挟みになりやすいのも要因です。
たとえば、分業型のインサイドセールス部門は、マーケティング部門とフィールドセールス部門の板挟みになるケースが少なくありません。
特に、インサイドセールスを導入しているにもかかわらず、組織のサイロ化が解消されていないケースでは、うまく連携が取れず部門間の板挟みになります。
フィールドセールスとの情報共有が難しい
フィールドセールスとの情報共有は、インサイドセールスの成功に不可欠ですが、営業手法の違いが情報共有のハードルを高くしているのも課題です。
対面営業と非対面営業では、必要な情報や担当者に求められるスキルが異なります。それぞれ重要視する要素が異なると、認識のズレが生じてスムーズに連携できません。
目標が定性的でイメージしづらい
獲得アポ数以外、目標が定性的でイメージしづらいのも、インサイドセールスの特徴であり課題です。
マーケティング部門やフィールドセールス部門は、目標や成果を定量的に設定し把握できます。
インサイドセールスの役割である「見込み顧客との関係性構築」「見込み顧客の育成」は、結果を具体的な数字で表せません。
こうした違いも、やめとけと言われる要因と考えられます。
顧客との信頼関係を築くまでに時間がかかる
そもそも、非対面の相手と良好な関係性を構築するには、長い時間が必要です。
インサイドセールスでは電話やメールを使用しますが、受注確度の高い見込み顧客でも、突然電話やメールが来れば警戒されることもあるでしょう。
地道に何度もアプローチを重ねながら、早くとも数か月、長ければ年単位で関係性を構築しなければなりません。
担当者には専門性の高いスキルや知識が求められる
担当者には、専門性の高いスキルや知識が求められます。
たとえば、フィールドセールス経験が長く多くの成果を挙げた担当者でも、インサイドセールスですぐに成功するとは限りません。
お互いの顔が見えない状態では「声のコミュニケーションスキル」や「傾聴力」などが求められます。
社内からの理解が得られにくい
インサイドセールスの導入には、組織改革が必要になるため、社内からの理解が得られにくいのも要因です。
スタッフによっては、部署異動で自身のスキルや経験を活かせないこともあります。新しいシステムやツールを導入しても、苦手意識を持つスタッフは受け入れがたいと思うこともあるでしょう。
新体制に納得できなければ、モチベーションの低下や離職につながりかねません。
インサイドセールス導入の課題を解決する方法5選

では次に、インサイドセールス導入の課題を解決する方法を紹介します。
- KGIやKPIは客観的に設定する
- インサイドセールスの役割を社内に周知して理解を得る
- 部門間の連携方法や体制を構築する
- ツールを活用する
- 内製化が難しいならアウトソーシングを検討する
以降でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
KGIやKPIを客観的に設定する
まず、KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)は、定量的に設定してください。
インサイドセールスは、目標が定性的でイメージしづらいのが課題です。そこで、KGIやKPIを設定すれば、目標を見える化できます。
目標が明確になればやるべきことを客観的に把握でき、達成感を得られればモチベーションアップにもつながるでしょう。
また、KPIは必ずKGIから逆算して設定すること、達成可能な数値であることも重要です。
インサイドセールスの役割を社内に周知して理解を得る
次に、インサイドセールスの役割を社内に周知して理解を得てください。
- インサイドセールスを導入する目的や理由
- インサイドセールスの業務内容
- 分業制の場合は各部門の役割
- 情報共有や連携の重要性
上記は一例ですが、定例会や社内報などで周知すれば理解を得やすくなるでしょう。必要に応じて研修の実施も検討してください。
事前に周知して社内からの理解を得られれば、インサイドセールスの導入で現場が混乱するのを防げます。
部門間の連携方法や体制を構築する
インサイドセールスにおいて、部門間の連携は不可欠です。
- 分業型:マーケティング部門・インサイドセールス部門・フィールドセールス部門
- 独立型:インサイドセールス部門がすべてを担当
- 協業型:状況に応じて分業型と独立型を併用する
このように、分業制のタイプでも役割は異なります。タイプは業種や商材によって異なるので、自社に合うタイプを見極め、連携方法や体制を構築してください。
なお、こちらの記事では、インサイドセールスの導入フローについて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
インサイドセールスの導入フローを徹底解説!成功のポイントも紹介
ツールを活用する
ツールは大いに活用してください。
インサイドセールスでは、MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理)などのツールが役立ちます。
ツールで事務作業を自動化すれば、個々の担当者にかかる負担を軽減できます。ツールに記録されるデータや履歴は、社内で情報を共有しやすくなるのもメリットの一つでしょう。
ただし、使いづらいと活用できません。誰でも使いこなせるように、直感的な操作が可能なツールを選ぶとよいでしょう。
こちらの記事では、インサイドセールスツールのおすすめと選定ポイントも解説していますので、参考にしてください。
インサイドセールスツールのおすすめ20選を徹底比較!選び方やメリットも紹介
内製化が難しいならアウトソーシングを検討する
社内体制の整備や、専門性の高いスキルや知識を持つ人材を確保できない場合は、アウトソーシングを検討してみてください。
ノウハウを持つプロが対応するので、導入からスムーズに稼働・運用が可能です。
外注コストはかかりますが、結果的に利益が向上すれば企業にとってもメリットになるでしょう。
インサイドセールスの導入が企業に与える5つのメリット

では次に、インサイドセールスの導入により、企業が得られるメリットを5つ紹介します。
- 成約率の向上が見込める
- 質の高いリードを獲得できる
- 属人化を解消できる
- 人手不足の解消につながる
- 多様な働き方に対応できる
成約率の向上が見込める
まず、成約率の向上が見込めます。
インサイドセールスは、顧客に信頼してもらえるように、関係性を構築するのが役割の一つです。
関係性を構築する過程では、見込み顧客の購買意欲も把握できます。信頼関係を構築したうえで、購買意欲が高いタイミングでアプローチすれば、成果につながりやすいでしょう。
質の高いリードを獲得できる
インサイドセールスには、見込み顧客の育成という役割もあります。
リードを獲得した時点では購買意欲が低くても、丁寧にフォローアップしながら関係性を構築するので、質の高いリードを獲得できます。
見込み顧客から顧客に転換できれば、リピーターの獲得やアップセル・クロスセルによる利益向上も見込めます。
属人化を解消できる
属人化を解消できるのも、大きなメリットです。
営業職は、個々の担当者に依存しやすい傾向があるため、属人化が起きやすいのが懸念点です。
インサイドセールスでは、複数の担当者で同一リードへの応対が基本です。
担当者が、個別に顧客情報や商談の進捗状況を管理する体制では、急遽担当者の変更があった場合に後任の担当者へスムーズな引き継ぎができません。
その点、チーム全体で情報を共有するインサイドセールスなら、このような状況でも属人化を解消できます。
人手不足の解消につながる
インサイドセールスの導入により、物理的な移動が不要になれば、一人の担当者が対応できる顧客数を増やせます。
また、アプローチできるエリアも増やせるので、限られたリソースでも営業活動を最大化できるのはメリットといえるでしょう。
現状のリソースで対応できれば、採用費や教育費の削減にもつながります。
多様な働き方に対応できる
そして、多様な働き方に対応できます。
インサイドセールスは、電話やメール・Web会議ツールを準備できる環境があれば、オフィスでもリモートワークでも対応が可能です。
たとえば、育児や介護中でも働けるようになるので、採用のハードルも下がるでしょう。
インサイドセールスの導入に向けて、人材を採用する予定がある企業にとっては、多様な働き方に対応しているとアピールできます。
インサイドセールスの導入で担当者が得られる5つのメリット

インサイドセールスの導入は、担当者にもメリットをもたらします。
- 担当者のスキルアップが期待できる
- データドリブンな営業が可能になる
- 実務を通して調整・交渉能力が身につく
- 顧客との関係性を構築するプロセスを学べる
- 企業の売上に貢献できる
以降で5つのメリットを紹介します。
担当者のスキルアップが期待できる
まず、担当者のスキルアップが期待できます。
非対面営業では、声でのコミュニケーションスキルや、声のトーンや話し方で相手の感情を理解するスキルなどが求められます。
また、顧客情報を収集するには、マーケティングスキルなども必要です。
営業だけでなく幅広い分野のスキルが身につけば、キャリアプランの選択肢も広がります。
データドリブンな営業が可能になる
データドリブンな営業が可能になるのもメリットです。
見込み顧客と関係性を構築する過程では、なかなか信頼してもらえないことも少なくありません。信頼関係を構築するためには、データに基づき客観的に判断することも大切です。
インサイドセールスでは、見込み顧客への理解を深め、最適なアプローチ方法やタイミングを見極めるために、多くのデータを扱います。
データドリブン営業が可能になれば、成功事例だけでなく失敗事例も活用でき、評価や判断の精度も高まります。
実務を通して調整・交渉能力が身につく
インサイドセールスは、他部門との連携が不可欠です。
情報を共有していても、認識のズレやスケジュール調整が必要になるケースは少なくありません。
認識のすり合わせやスケジュール調整など、実務を通じて調整力や交渉能力が身につきます。調整力や交渉能力は他の職種にも活かせるので、将来的なキャリアチェンジにもつながるでしょう。
顧客との関係性を構築するプロセスを学べる
顧客との関係性構築は、インサイドセールスに限らずあらゆる職種でも重要な要素です。
自社商材に関心や興味がある顕在層でも、簡単には信頼関係を構築できません。
その点、インサイドセールスは、必然的に顧客との関係性を構築するプロセスを学べます。
また、務を通じてさまざまなパターンを繰り返し学べるのも、営業担当者には大きなメリットになるでしょう。
企業の売上に貢献できる
顧客から信頼できる企業、または担当者との理解を得られていれば、見込み顧客から顧客に転換できる可能性があります。
さらに、継続的にフォローアップしてリピーターを獲得できれば、アップセル・クロスセルにつながるかもしれません。結果として企業の売上に貢献できます。
インサイドセールス導入支援ならディグロス

インサイドセールスの導入を検討していても、社内体制の整備や人手不足などの課題があり実現できないケースは少なくありません。
このような課題の解決には、株式会社ディグロスのセールスストラテジーコンサルティングがおすすめです。
弊社は業界トップクラスを誇る、セールス×アウトバウンドにおける15年以上の経験とノウハウを活かして、さまざまなニーズに対応できるサービスを提供しています。
これまで3,000社に対して、年間3,400のプロジェクトを提供している、インサイドセールス導入支援実績もございます。
インサイドセールス導入支援をご検討中の企業様は、電話やメールでご説明しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:インサイドセールスはやめとけはウソ!多くのメリットがある

インターネット上には、インサイドセールスはやめとけという意見も散見されますが、実際には多くのメリットがあります。
スムーズに導入するには、事前の社内周知と理解、そして体制の整備が必要です。もし立ち上げに不安がある場合は、コンサルティングの利用で解決できる場合もあります。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、インサイドセールスを導入して成果につなげてください。