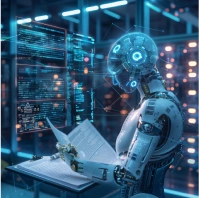税理士の営業ガイド!営業手法13選や禁止事項について解説

税理士業界は競争が激しく、経営を安定させるためには、顧客獲得のための営業が不可欠です。
しかし、効果的な営業方法がわからず、なかなか集客につながらないと悩んでいる税理士もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、税理士が知っておくべき営業手法13選や、見落としがちな禁止事項まで詳しく解説します。効果的に営業活動を行う7つのコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
税理士に営業力が求められる理由

では早速、税理士に営業力が求められる3つの理由を紹介します。
- 新規顧客を獲得するため
- 強みをアピールして差別化を図るため
- 顧客との関係性を構築するため
新規顧客を獲得するため
近年、税理士業界は、DX化やAIの普及により従来の業務が効率化され、記帳代行などのニーズが縮小傾向にあります。
また、税理士の数自体も増加しており、市場の競争が激化しています。そのため、ただ待っているだけでは新規顧客の獲得が困難です。
事務所の経営を安定させるためには、自ら積極的に営業活動を行い、顧客獲得に取り組む必要があります。
強みをアピールして差別化を図るため
営業は競争が激化する現代において、自社の強みをアピールし他事務所との差別化を図るための重要な手段です。
その手段として、以下のような営業活動が挙げられます。
- 専門性の可視化:特定の業種や分野に特化した知識や実績をアピールする
- サービスの付加価値:経営コンサルティングなど付加価値の高いサービスを提供していると伝える
- 人柄と信頼関係の構築:税理士自身の人柄や考え方を伝え信頼関係構築する
こうした活動を通じて競合との差別化を図れば、選ばれる理由を顧客に提示できます。
顧客との関係性を構築するため
税理士にとっての営業は、単に契約を取るための活動ではなく、顧客との間に信頼関係を築くために不可欠なプロセスです。
顧客は、自身の重要な情報を安心して任せられる専門家を求めています。
だからこそ、顧客の悩みや課題に真摯に耳を傾け、的確なアドバイスを提供し「この人になら任せられる」という安心感を与えることが重要です。
税理士の営業手法13選

それでは、税理士の主な営業手法13選を紹介します。
- テレアポ営業
- チラシ営業
- 訪問営業
- 士業交流会
- 既存顧客からの紹介
- 金融機関からの紹介
- ホームページ
- フォーム営業
- 専門記事の執筆や監修
- SNS運用
- 広告
- 勉強会やセミナー
- 税理士紹介サービス
テレアポ営業
テレアポ営業は、見込み顧客に電話をかけてアポイントを獲得する手法です。
新規顧客の開拓を目的とし、企業の経営者や経理担当者などに直接アプローチすることで、自社のサービスを説明する機会を得られます。
テレアポは相手の顔が見えないため、声のトーンや話し方、簡潔で分かりやすい説明が成功の鍵となります。
また、断られることも多いため、精神的なタフさも求められます。
もし、自社でのテレアポでなかなか成果が出ない場合は、テレアポ代行サービスの利用も一つの選択肢です。ノウハウを持つプロが効率的にアポイントを獲得してくれるため、税理士は本業に集中できます。
チラシ営業
チラシ営業は、事務所の所在地周辺の企業や個人事業主に向けて、チラシを配布する手法です。
- 記載内容:サービス内容・料金・事務所の強み・実績・連絡先など
- 配布方法:地域のフリーペーパーへや新聞の折り込み・ポスティング・手渡しなど
ただし、チラシは多くの情報の中から埋もれてしまう可能性も高いため、ターゲットを絞り、目を引くデザインやキャッチコピーを工夫する必要があります。
訪問営業
訪問営業は、見込み顧客となる企業や個人事業主のもとへ直接訪問する手法です。
直接顔を合わせることで、話し方や雰囲気を伝えられ、顧客は安心して相談できます。これにより、深い関係性を構築しやすいのが大きな特徴です。
訪問営業を成功させるには、事前の準備が欠かせません。訪問先の顧客情報を事前に調べ、経営課題を想定しておくことで、相手に合わせた効果的な提案が可能になります。
士業交流会
士業交流会には、税理士だけでなく、弁護士・司法書士・行政書士といった他の専門家が集まります。
こうした交流会に参加する最大のメリットは、参加者から顧問先を紹介してもらえる可能性があることです。
また、専門分野が異なる士業との連携により、顧客の多様なニーズにワンストップで対応できる体制を構築できます。これは、顧客の利便性を高めるだけでなく、自社の強みにもなります。
交流会で名刺交換をする際には、自分の専門分野や強みを明確に伝えると効果的です。
既存顧客からの紹介
既存顧客からの紹介は、新規顧客を獲得するうえで効果的な方法の一つです。
顧問契約を結んでいる顧客からの紹介は、信頼関係がすでに構築されているため、スムーズに話が進みやすく契約に至る可能性が高いという特徴があります。
また、営業にかかるコストをおさえられる点も大きなメリットです。
既存顧客からの紹介を増やすには、日頃から丁寧な対応を心がけ、顧客満足度を高めることが大切です。
定期的なコミュニケーションを図りながら、顧客の経営状況や課題を深く理解し、期待を上回るサービスを提供すれば、自然と紹介が生まれるようになるでしょう。
金融機関からの紹介
金融機関は、融資や事業計画の相談を通じて多くの経営者と接するため、税務や会計の課題を抱える顧客を紹介してくれる場合があります。
ただし、顧客を紹介してもらうには、金融機関の担当者との信頼関係が欠かせません。税務の最新情報を提供したり、職員向けの勉強会を開催したりして、専門性をアピールしましょう。
また、顧問先が融資を必要とする際には、金融機関とスムーズに連携できる体制を整え、連携実績を積み重ねることも重要です。
ホームページ
ホームページは、名刺では伝えきれない多くの情報を提供でき、24時間365日新規顧客を呼び込んでくれる強力なツールとして活用できます。
ホームページ活用のポイントは、以下の通りです。
- 強みを明確にする:特定の業種に特化している場合は強調する
- 信頼性を確保する:プロフィール・料金体系・顧客の声などを掲載する
- 役立つ情報・コンテンツを発信する:税務や経営に関する情報など
- 問い合わせ導線を分かりやすく配置する:相談フォームや電話番号など
なお、ホームページは一度作って終わりではありません。
常に情報を更新し、訪問者にとって価値のあるコンテンツを提供し続ければ、集客効果を高められます。
フォーム営業
フォーム営業は、企業のウェブサイトにある「問い合わせフォーム」を利用して営業を行う手法です。
電話やメールに比べて相手の時間を奪うことがなく、担当者へ直接メッセージを届けられるため、近年注目されています。
しかし、手軽に始められる反面、反応率が低いというデメリットもあります。
以下の点を意識しながら、フォーム営業を効果的に活用しましょう。
- ターゲットを絞る
- パーソナライズされた内容にする
- 具体的な提案を盛り込む
- メリットを具体的に提示する
- 送信時間帯を考慮する
これらの工夫を盛り込むことで、担当者の目に留まり返信につながる可能性が高まります。
専門記事の執筆や監修
専門記事の執筆や監修は、税理士としての信頼性や専門性をアピールするうえで、非常に効果的な手法です。
専門メディアやビジネス雑誌に寄稿したり、ウェブサイトでコラムを執筆したりすることで、単なる名刺交換や広告だけでは得られない関係性を構築できます。
定期的に記事を執筆することで、専門家としてのブランドが確立され、将来的に「この税理士に相談したい」と思ってもらえる可能性が高まります。
SNS運用
SNSは、税理士のブランドを確立し、潜在顧客との接点を持つための強力なツールです。情報拡散力が高いという特性を活かせば、より多くの人々にリーチできます。
ただし、SNS運用では、プラットフォームによって特徴が異なるため、目的やターゲットに合わせて選ぶ必要があります。
- X(旧Twitter):短い文章でスピーディに専門家としての知見を発信できる
- Instagram:視覚的にわかりやすくアピールできる
- Facebook:実名登録制のため投稿の信頼性が高い
- YouTube:動画でわかりやすく伝えられ検索からの流入が期待できる
このような特徴を踏まえて、単独で使うだけでなく連携させて運用するのも効果的です。
広告
広告は、税理士事務所の存在を、短期間で多くの人に知ってもらうための有効な手段です。
ターゲットを絞り込んで集中的にアプローチできるため、効率的な新規顧客獲得が期待できます。
なお、広告には「オンライン広告」と「オフライン広告」があり、それぞれ特徴が異なることに留意しましょう。
オンライン広告は、特定のキーワードで検索している人や特定の属性を持つ人に絞って表示できるため、高い費用対効果が期待できます。
一方、オフライン広告は、専門誌や地域情報誌への掲載を通じて、特定の業界や地域に特化した顧客獲得に効果的です。
なお、広告はすぐに成果が出やすい反面、ある程度の費用がかかります。とはいえ、戦略的に活用すれば、自社の強みを必要とする見込み顧客に効率的にアプローチできるでしょう。
勉強会やセミナー
勉強会やセミナーは、税理士の専門知識を直接アピールし、潜在顧客との信頼関係を築くための効果的な手法です。
参加者には無料で役立つ情報が得られるメリットがあり、税理士は見込み顧客と直接会って話せる貴重な機会を得られます。
オンラインとオフライン、どちらの形式でも開催が可能です。
参加者との対話を通じて有益な情報を提供できれば「この税理士に相談したい」という気持ちを自然に引き出せるでしょう。
税理士紹介サービス
税理士紹介サービスは、専門性や得意分野に合った見込み顧客を、サービス運営会社が代わりに探して紹介してくれます。
自分で営業活動を行う手間や広告費を大幅に削減できるうえ、サービスを利用する見込み顧客はすでに税理士を探す意思が固まっているため、契約に至る可能性が非常に高いです。
特に、営業活動に割くリソースが限られている場合に有効な手法といえます。
税理士の営業活動における禁止事項

税理士の営業活動は、その信用性を維持するために法律や倫理規定によって厳しく制限されています。
ここでは、税理士の営業活動における禁止事項や行為について詳しく解説します。
- 過度な表現を使用しない
- 国税局での経験を詳細に記載しない
- 他の税理士と比較しない
- 他の税理士の顧問先は避ける
- 広告ガイドラインを遵守する
過度な表現を使用しない
税理士の営業活動では、顧客を誤解させるような過度な表現や誇大広告は禁止されています。
具体的には、以下のような表現が該当します。
| NGな表現 | 理由 |
|---|---|
| 必ず節税できます | 節税対策には、個々の状況が影響するため断定的に表現できない |
| 税務調査で追徴課税ゼロを保証します | 税務調査の結果は、事前に保証できない |
| 業界最安値 | 料金体系は事務所ごとに異なるため、具体的な根拠がない |
参照:業務広告に関する指針|第3 規程第3条の規定により規制される広告
このような表現を使用すると、税理士としての信頼を損なう恐れがあります。
税理士の営業活動では、具体的な実績やサービス内容を正確に伝えましょう。
国税局での経験を詳細に記載しない
税理士の経歴として、国税局での勤務経験は大きな強みとなります。しかし、その経験を営業活動で詳しく語ることには注意が必要です。
「国税局にいたから、税務調査に関する情報を知っています」
「現役時代に経験した〇〇社の事例では……」
このような表現は、秘密を守る義務(法第38条)に違反する恐れがあります。
参照:6 税理士法違反行為|【税理士が遵守すべき主な税理士法上の義務等】
国税局での経験を強みにしたい場合は「元国税調査官としての豊富な経験を活かし、税務調査の際にも適切なアドバイスを提供します」のように抽象的な表現にとどめましょう。
他の税理士と比較しない
税理士の営業活動において、他の税理士や事務所と比較する行為は避けるべきです。
「他の事務所よりも安く請け負います」
「〇〇事務所のやり方は間違っています」
このような表現は、品位を損なう行為として税理士法第1条の「税理士の使命」に反するだけでなく、顧客からの信頼を失う原因にもなります。
参照:国税庁|1 税理士の使命
「お客様の事業計画策定から資金調達まで、トータルでサポートします」
このように、他の税理士と比較はせず、自身の強みやサービス内容に焦点を当てるとよいでしょう。
他の税理士の顧問先は避ける
税理士の営業活動では、他の税理士と契約している顧問先を、意図的に奪うような行為は避けるようにしましょう。
参照:○○税理士会綱紀規則(準則)|業務侵害行為の禁止 第25条
「他の税理士よりも顧問料を大幅に値下げして契約を促す」
このような行為は、顧客との間でトラブルを引き起こす原因になるだけでなく、業界全体の信用を損なうことにもつながりかねません。
税理士業界の秩序と品位を守るためにも、ルールを守ることが大切です。
広告ガイドラインを遵守する
税理士の広告活動は、これまで紹介した禁止事項の他にも「顧問先名の無断掲載」や「顧客の不安を煽るような内容」などにも注意が必要です。
ガイドラインを遵守することは、コンプライアンス上の義務であると同時に、税理士としての信頼性を高める上でも非常に重要です。
正直で誠実な情報発信を心がけながら、顧客との長期的な関係を構築しましょう。
税理士が営業活動を効果的に行う7つのコツ

士業の中でも特に競争が激しい税理士業界で、顧客を獲得するための効果的な営業活動のコツを7つ紹介します。
- ターゲットを明確にする
- マーケティング活動を積極的に行う
- 過去の実績をアピールする
- 専門分野に特化しすぎずバランスよく対応する
- 顧客の課題やニーズにマッチした提案をする
- 継続的に集客できる仕組みを作る
- 営業代行サービスを活用する
ターゲットを明確にする
税理士の営業活動で最も重要なことの一つは「誰にサービスを提供したいのか」そのターゲットを明確にすることです。
ターゲットを絞らずに闇雲にアプローチすると、メッセージが誰にも響かず、効率的な集客は望めません。
そこで、ターゲットを絞り込めばメッセージが響きやすくなり、自身の専門性が際立ちます。結果として、本当に必要としている顧客に向けて、効率的にアプローチできるでしょう。
マーケティング活動を積極的に行う
税理士の営業については、積極的なマーケティング活動も不可欠です。
特に、オンラインとオフラインを連携させる「O2Oマーケティング」を活用しましょう。
- オンライン(ウェブサイト・SNSなど)で情報を発信する
- 情報に関心を持った見込み顧客をオフライン(セミナー・交流会)に誘導する
このように、オンラインとオフラインを連動させることで、潜在顧客の関心を引いてから、見込み顧客を顧客に転換する手法です。
また、マーケティング活動は、短期的な成果だけでなく長期的な視点で行うことで、安定した集客基盤を構築できます。
過去の実績をアピールする
過去の実績は、税理士としての専門性や信頼性を客観的に証明できます。
アピールする際は、口頭での説明だけでなく、具体的な数字や事例を示すことも重要です。
- 実績を具体的に提示する:税務に関する支援歴〇〇年で、支援社数〇〇社です
- 顧客の声を取り入れる:専門用語を使わずわかりやすく説明してくれた
このように、具体例を示すと、顧客はサービス内容や価値をイメージしやすくなります。
専門分野に特化しすぎずバランスよく対応する
特定の専門分野に特化することで強みをアピールできます。
しかし、それにこだわりすぎると、顧客層が限定され、新たな分野のニーズに対応できない恐れがあります。
ビジネスチャンスを広げるには、幅広い顧客に対応できる柔軟性が不可欠です。
専門分野で強みをアピールしつつ、多様な課題に対応できる「応用力」をアピールすれば、特定の分野に依存せず持続的に顧客を獲得できるでしょう。
顧客の課題やニーズにマッチした提案をする
そもそも、顧客は「経理や会計が苦手で、本業に集中したい」「将来の資金繰りが不安で、事業を安定させたい」などの課題を税理士に依頼します。
過去の実績や専門知識をアピールしても、それが自分の課題をどう解決してくれるかを理解できなければ依頼したいと思ってもらえないでしょう。
まずは、丁寧なヒアリングを通じて「顧客が何に困っているのか」「何を求めているのか」真の課題とニーズを把握しましょう。
そのうえで「経理業務の効率化」「資金繰りの改善」といった顧客が抱える、具体的な課題に焦点を当てた提案を行うことが重要です。
継続的に集客できる仕組みを作る
税理士には、年間を通じて業務が集中する繁忙期があります。
- 2月〜3月(確定申告)
- 5月(法人税申告)
- 11月〜12月(年末調整)
上記は税理の繁忙期であり、この時期は業務量が増加します。
しかし、繁忙期が過ぎると、一時的に仕事が減り、安定した収入が得られないという課題に直面することがあります。
このような状況を避け経営を安定させるには、継続的に集客できる仕組みを作ることが不可欠です。
Webサイトやブログ、SNSやメルマガなどを活用しながら、継続的に見込み顧客が集まる仕組みを構築しましょう。
営業代行サービスを活用する
自身では成果が出ない場合や、営業にリソースを割けない場合は、営業代行サービスを活用する選択肢もあります。
ノウハウを持つプロが、営業活動を代行するので、税理士は本業に集中しながら効率的に新規顧客を獲得できるのがメリットです。
一方で、営業活動を外部に任せるため、自社に営業ノウハウが蓄積されにくく、代行会社との連携が不十分だと情報共有が滞る可能性があります。
営業代行サービスを活用する際は、事務所の理念や専門性を理解してくれるかを確認しましょう。
税理士の営業・テレアポ代行ならディグロス

営業代行会社といってもさまざまあるため、何を基準に選べばいいか迷うこともあるでしょう。
税理士の営業・テレアポ代行なら、2,000社以上の支援実績を持つ、株式会社ディグロスにお任せください。
弊社のテレアポは「アポイント獲得」と「プロデュース力」に特化しているので、営業業務の効率化や、成果を最大化したいお客様におすすめです。
あらゆる業種での実績と、事業開始から16年間蓄積されたノウハウを武器に、成果報酬型でお客様のご要望に沿った形のアポイントメント(商談の場)をセッティングします。
過去には「税理士法人(税務サポート・コンサルティング)会社 様」や「税理士法人様の顧問先開拓プロジェクト」の支援実績もございます。
税理士の営業・テレアポ代行をご検討中のお客様には、電話やメールでご説明いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:税理士こそ営業活動は不可欠!

税理士の営業活動は、単に顧客を獲得するだけでなく、安定した経営基盤を築くために不可欠です。
しかし、税理士は、繁忙期に業務量が集中する一方で、それを過ぎると依頼が減少し収入が不安定になるという課題があります。
こうした業務量の変動をなくし、安定した収入を確保するには、年間を通して集客できる仕組みを作ることが大切です。
本記事で紹介した情報を参考に、自身の強みや専門性を活かした効果的な営業活動を進めてください。