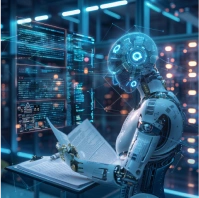BANTとは?情報の聞き方や活用術・役立つフレームワークを解説

複数の商談を抱えていると、どれから優先すべきか迷うこともあるでしょう。商談に進んでも、成約につながらず悩んでいる方もいるかもしれません。
このような課題を解決し、営業活動の効率化を図るために不可欠なのが、BANTです。
本記事では、商談のヒアリングに不可欠なフレームワーク「BANT」について、情報の効果的な聞き方や活用術を解説します。BANTと合わせて活用できる他のフレームワークも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
BANT(BANT条件)とは?
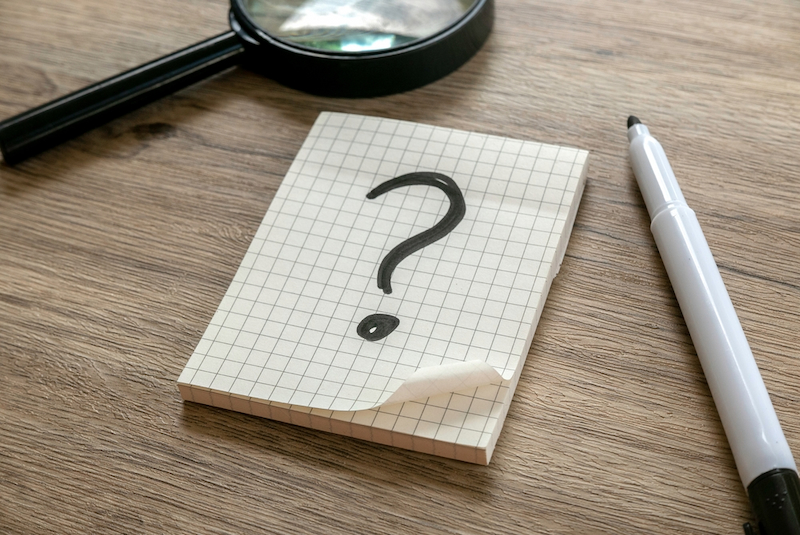
BANTは、ヒアリングに必要な4要素の頭文字を取ったもので、商談の成約率を判断するために活用されるフレームワークです。
- Budget(予算)
- Authority(決裁権)
- Needs(必要性)
- Timeframe(導入時期)
各要素を以降でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
Budget(予算)
Budgetは、顧客が商材を購入するにあたって、どのくらいの予算を確保しているかを明確にします。
自社商材が顧客ニーズにマッチしていても、予算を確保できなければ成約には至りません。
また、顧客の予算を把握できていれば、適切なプランを提案できるようになります。
Authority(決裁権)
Authorityは、決裁権を持つ人にアプローチできているかを判断する要素です。
商談がスムーズに進んでも、担当者に決裁権がなければその場では最終的な成約には至りません。
そこで、ヒアリング時に決裁権を持つ人の特定と把握ができれば、無駄なやりとりを減らし、成約までの時間を短縮できます。
決裁権を持つ人に直接アプローチすることで、成約につながりやすくなるのもメリットです。
Needs(必要性)
Needsは、顧客が抱える課題やニーズを判断する要素です。
そもそも、自社商材がどれほど優れていても、ニーズにマッチしていなければ提案を受け入れてもらえない恐れがあります。
そこで、ヒアリングを通じて顧客の潜在的な課題を深く理解することで、自社商材が課題解決に役立つことを具体的に提案できます。
その結果、商談を有利に進められれば、成約につながりやすくなるでしょう。
Timeframe(導入時期)
Timeframeは、顧客がいつまでに商品やサービスを導入するかを判断する要素です。
導入時期が曖昧だと、商談の優先順位をつけづらく、具体的なスケジュールを提案できません。
判断を見誤り、早急に導入したいと考えている顧客を後回しにしてしまうと、機会損失のリスクが高まります。
ヒアリング時に明確な導入時期を把握できていれば、具体的なスケジュールを提案でき、クロージングまでスムーズに進められるでしょう。
BANTを営業に活用する4つのメリット

それでは、BANTを営業に活用することで得られる4つのメリットを紹介します。
- 顧客に寄り添った営業ができる
- アプローチの優先順位が明確になる
- 受注までのプロセスを定量的に把握できる
- チーム内でスムーズに情報を共有できる
顧客に寄り添った営業ができる
まず、顧客に寄り添った営業ができます。
特に初回のヒアリングでは、顧客との関係性を構築できていないため、一方的に売り込めば顧客に不信感を抱かれるかもしれません。
一度でも悪い印象を与えてしまうと、挽回するのは困難です。
一方的に売り込むのではなく、顧客の状況に合わせて適切な提案ができれば、信頼関係を構築でき、成約率の向上につながるでしょう。
アプローチの優先順位が明確になる
アプローチの優先順位が明確になるのは、大きなメリットです。
BANT情報の活用により、成約率を客観的に判断できれば優先順位をつけやすくなります。
優先順位の高い商談から進めていけば、優先度の高い商談に集中でき、営業活動全体の効率化につながるのもメリットです。
受注までのプロセスを可視化できる
BANTは、商談の進捗状況を客観的に把握できるといった側面もあります。
仮に複数の商談を抱えていても、各商談のBANT情報を整理すれば、営業プロセスを可視化でき、その結果売上の予測精度も向上するでしょう。
さらに、全体のプロセスが可視化されることで、ボトルネックを特定しやすくなります。
たとえば、Authorityの段階で商談がストップしているなら、ヒアリング方法の見直しで改善が可能です。
チーム内でスムーズに情報を共有できる
BANT情報を活用すれば、チーム内でスムーズに情報共有できます。
たとえば、途中で担当者が代わり引き継ぎが必要になった場合でも、BANT情報が整理されていれば担当者はスムーズに情報を把握できます。
また、全体の営業プロセスが可視化されるため、営業マネージャーはリアルタイムで進捗状況を把握できるのもメリットです。
その結果、適切なアドバイスやサポートが可能になれば、商談の質が向上しチーム力の強化にもつながります。
BANTの営業における活用術

では次に、BANTの営業における活用術を5つ紹介します。
- 予算は早い段階で把握する
- 決裁ルートを確認する
- 根回しの方法を確認する
- 潜在的なニーズや課題も意識する
- 具体的なスケジュールを提案する
予算は早い段階で把握する
予算は早い段階で把握しておきましょう。
商談の初期段階で予算を把握できていれば、自社商材が予算内に収まるかを判断できます。
仮に予算が合わなかった場合は、他の商品や別のプランを提案するなど、軌道修正が可能です。早い段階で代替案を用意できれば、営業活動の無駄を省けます。
予算が明確であれば、顧客も安心して商談を進められるようになり、その結果信頼関係を構築しやすくなります。
決裁ルートを確認する
決裁ルートの確認は、スムーズに商談を進めるうえで非常に重要です。
たとえば「担当者から部長→部長から役員→役員から決裁者」のように、決裁ルートが複数に及ぶケースは少なくありません。
こうしたケースでも、各段階でどのような承認が必要なのかを理解できていれば、商談の停滞を防ぎ成約までの時間を短縮できます。
根回しの方法を確認する
顧客によっては、決裁者への直接的なアプローチが難しい場合があります。
このようなケースでは、根回しの方法を確認しましょう。
たとえば、担当者から決裁者に話を通す際に必要な情報を把握できていれば、事前に決裁者に向けたプレゼン資料を用意できます。
担当者にプレゼン資料を渡せば、スムーズに商談を進められるでしょう。
潜在的なニーズや課題も意識する
そして、すでに言語化できている明らかなニーズだけでなく、顧客自身が気づいていない潜在的なニーズも意識してください。
ヒアリングで顧客の潜在的な課題を引き出せれば、顧客のことを深く理解しようとしている姿勢をアピールできます。
真摯に寄り添ってくれていると感じてもらえれば、顧客から信頼されやすくなります。
この先に起こり得るリスクに対する解決策を提案できれば、関係性を構築しやすくなり、成約率の向上につながるでしょう。
具体的なスケジュールを提案する
導入時期を把握できたら、具体的なスケジュールを提案しましょう。
単に導入時期を質問するのではなく、顧客の希望に合わせた具体的なスケジュールの提案を意識してください。
こうすることで、商談を現実的に捉えられるからです。
その結果、顧客は導入までのプロセスをイメージしやすくなり、購買意欲を高める効果が期待できます。
BANTを活用する際の注意点

BANTを活用する際は、いくつか注意したい点があります。
- BANTは営業のヒアリングで設定する必要がある
- 質問攻めはせず自然な会話を意識する
- 日本企業のカルチャーを考慮する
- 状況に応じてBANT以外のフレームワークも活用する
- 情報不足によるリスクに注意する
以降で5つの注意点を詳しく解説します。
BANTは営業のヒアリングで設定する必要がある
BANTは、営業のヒアリングで設定する必要があることに留意しましょう。
ヒアリングに不可欠なフレームワークでも、単なるチェックリストになれば顧客との関係性は構築できません。アンケートの実施でも集計はできますが、より踏み込んだ情報の取得は難しいでしょう。
直接営業で必要な情報を引き出すように意識しながら、顧客に寄り添い商談を進めることも重要です。
質問攻めはせず自然な会話を意識する
情報を引き出したいあまりに、質問攻めにすると顧客に不信感を与える恐れがあります。
冒頭で突然「予算はいくらですか?」「決裁権を持つのは誰ですか?」など質問攻めにするようなことは避けてください。
そこで、オープンクエスチョンを活用すれば、自然に会話を展開できます。
オープンクエスチョンなら、回答が限定されないので相手は自由に答えられます。
たとえば、「導入にあたって、どのようなスケジュールを想定されていますか?」と質問すれば、顧客の要望を聞きながら具体的に提案できるでしょう。
日本企業のカルチャーを考慮する
BANTは海外で生まれたフレームであるため、そのままでは日本のビジネスカルチャーにマッチしないケースがあります。
たとえば、日本企業の多くは決裁者が複数にわたる傾向があるため、Authorityでは決裁権を持つ人だけでなく、決裁ルートの確認が不可欠です。
また、初期段階では予算が決まっていないケースもあるため、Budgetを聞き出すタイミングを見極める必要があります。
状況に応じてBANT以外のフレームワークも活用する
BANTはヒアリングに不可欠なフレームワークですが、状況によっては必要な情報を引き出せないケースがあります。
BANTだけに囚われず、状況に応じて他の情報にも目を向けて収集してください。
なお、その他のフレームワークについては、「BANTに関連する他のフレームワークやテクニック」で詳しく解説しますが、使い分けることで営業活動を効率的に進められます。
情報不足によるリスクに注意する
そして、情報不足によるリスクに注意してください。
ヒアリングした情報が不足したままでは、失注リスクが高まるからです。
各要素で情報が不足した場合のリスクを以下にまとめます。
| 要素 | リスク |
|---|---|
| Budget(予算) | 予算を確保できないと商談が進まない 値引き交渉の長期化が懸念される |
| Authority(決裁権) | 導入までに時間がかかり営業プロセスが進まない |
| Needs(必要性) | 提案を受け入れてもらえない |
| Timeframe(導入時期) | 優先順位を見誤る恐れがある 適切なタイミングでアプローチできず失注する |
このようなリスクを避けるためにも、BANTを活用する際は、4つの情報を十分に揃えることを意識しましょう。
BANTに関連する他のフレームワークやテクニック

それでは、BANTに関連する他のフレームワークやテクニックを紹介します。
- BANTC
- BANTCH
- GPCTBA/C&I
- MEDDIC
- SPIN話法
BANTC
BANTCは、BANTにCompetitor(競合)を加えた5つの要素で構成されています。
顧客が複数のサービスや商品を比較検討している段階では、競合他社との差別化が不可欠です。もし、差別化できなければ競合他社に負ける恐れがあります。
BANTだけでは、競合他社の情報を収集できません。
そこで、BANTCを活用して競合他社との差別化を図れば、市場での優位性を確立できるでしょう。
BANTCH
BANTCHは、BANTCにHuman resources(人的資源)を加えた6つの要素で構成されています。
商品やサービスの導入に際して、顧客の組織体制や役割分担の把握が必要です。
ヒアリングで人的資源を把握できていれば、調整が必要な場合は、適切な部署や担当者に働きかけ、導入後の運用をスムーズに進めるための準備ができます。
たとえば、リソース不足の課題を抱えている場合は、運用代行サービスの提案など具体的な解決策を提示して顧客の不安を解消できます。
GPCTBA/C&I
GPCTBA/C&Iとは、マーケティングと営業を最適化するフレームワークであり、以下の要素で構成されています。
- Goals(目標):顧客が目指すゴール
- Plans(計画):目標達成に向けた計画の把握
- Challenges(挑戦):目標達成の障壁を把握し解決策を提案する
- Timeline(タイムライン):商品・サービスの導入時期
- Budget(予算):顧客の予算
- Authority(権限):決裁者の把握
- Negative Consequences(否定的な結果):リスクと解決策の提案
- Positive Implications(肯定的な結論):自社商材を導入するメリットやベネフィットを強調
このように、GPCTBA/C&IにはBANTの要素も含まれており、包括的に顧客への理解を深められるのが特徴です。
MEDDIC
MEDDICは、BANTよりも複雑な購買プロセスで、受注確度を判断するフレームワークです。
- Metrics(指標):導入にあたって顧客が抱く期待値
- Economic Buyer(経済的購買者):最終的な決定権を持つ人物
- Decision Criteria(意思決定基準):導入を決める判断基準
- Decision Process(意思決定プロセス):購入までのプロセス
- Identify Pain(課題の特定):顧客が抱える課題(顕在的・潜在的)
- Champion(支持者):購入をサポートする人
BANTと併用すれば、商談の全体像を深く理解できます。特に、長期的かつ複雑なプロセスの商材に適しています。
SPIN話法
SPIN話法は、顧客の潜在的ニーズを引き出すのに役立つ、ヒアリングテクニックです。
- Situation Questions(状況質問):顧客の状況を正確に把握する
- Problem Questions(問題質問):顧客が気づいていない問題を明確にする
- Implication Questions(示唆質問):潜在ニーズを顕在化する
- Need-payoff Questions(解決質問):課題の解決で得られるメリットをイメージできる
SPIN話法は、潜在課題やニーズを顧客に気づかせるために行います。
BANTと併用すれば、商談初期からクロージングまで戦略的な営業活動を実現できるでしょう。
テレアポ代行ならディグロス

BANTは、ヒアリングを優位に進められるフレームワークですが、そもそも商談のアポイントを獲得できなければ受注にはつなげられません。
電話で見込み顧客にアプローチするテレアポは、飛び込み営業のように訪問先を回る時間や交通費がかからないため、限られた時間でより多くの見込み顧客にアプローチできます。
しかし、電話では表情や熱量が伝わりづらく、対面での営業に比べて信頼関係を築きにくいのが課題です。また成功率が1%程度しかないため、アポイントを獲得するには専門性の高いスキルが不可欠です。
内製化が難しいのであれば、2,000社以上の支援実績を持つ株式会社ディグロスにお任せください。
弊社では、成果報酬型のテレアポ代行サービスを提供しています。
「アポイントメント獲得」「プロデュース力」に特化しているので、営業業務の効率化や成果の最大化を目指すお客様におすすめです。
テレアポ代行をご検討中の企業様には、電話やメールでご説明しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:BANTの活用で商談品質を高めて成約につなげよう

BANTは、4つの要素をヒアリングで確認し、営業活動の効率化に役立つフレームワークです。
顧客への理解を深め、寄り添った提案を可能にするので、関係性を構築しやすくなります。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、BANTの活用で商談の質を高めて成約につなげてください。