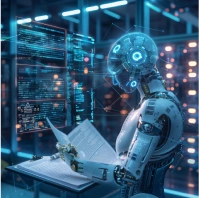商談分析とは?実施する目的や手法・フレームワークを紹介

インターネットの普及やコロナ禍などの影響から、オンライン商談を導入する企業が増えています。
対面商談とは異なりお互いの温度感を把握しづらいため、成約を獲得できないケースは少なくありません。
そこで商談分析を実施すれば、課題の把握と改善が可能です。
とはいえ、商談分析にはメリットとデメリットが存在しており、状況に応じて適切な施策を見極める必要があります。
本記事では、商談分析の目的やメリット・デメリットを紹介します。できることや手法・フレームワークについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
商談分析をする目的

では早速、商談分析をする目的を5つ紹介します。
- 課題を抽出して改善に活かす
- 顧客ニーズを正しく理解する
- 売上予測を立てる
- 属人化を防ぐ
- ノウハウを共有する
課題を抽出して改善に活かす
まず、課題を抽出して改善に活かす必要があります。
一口に商談といっても、見込み顧客の選定から契約の獲得まで、いくつかのフェーズに分かれており、どこに課題が潜んでいるかを見極めるのは困難です。
フェーズごとに商談分析をすれば、どこに課題があるのかを把握できます。解決すべき課題が明確になれば、解決に向けて適切な解決策を立案できるでしょう。
顧客ニーズを正しく理解する
インターネットの普及により、顧客は欲しい情報を手軽に入手できます。
自社商品やサービスを訴求しても、すでに顧客が必要な情報を入手しており、比較検討の段階に入っていれば効果的な訴求はできません。
そこで顧客ニーズを正しく理解するためにも、商談分析が重要な意味を持ちます。
商談分析により顧客自身が気づいていない潜在ニーズを引き出せれば、競合他社との差別化を図り、信頼できる企業だとアピールできます。
売上予測を立てる
そして、売上予測を立てる際にも商談分析が役立ちます。
売上予測は、企業が安定した経営を実現するために欠かせない施策です。
商談分析により売上予測精度が向上すれば、正確な売上予測が可能になるでしょう。
属人化を防ぐ
営業職は特定の担当者に依存しやすく、属人化しやすいのが課題です。
顧客情報や進捗状況を把握している担当者が不在の場合は、その他のスタッフが対応できません。
そこで商談分析結果を見える化して社内で共有すれば、属人化の防止が期待できます。
ノウハウを共有する
ノウハウを共有するといった目的もあります。
成約を獲得できなくても、原因と解決方法を社内で共有すれば、営業力の底上げや応対品質の標準化を図れます。
トップセールスのノウハウは、人材育成やマニュアルの作成にも活用が可能です。
商談分析でできること8選

では次に、商談分析でできることを8つ紹介します。
- 商談内容をテキスト化する
- コンプライアンスを強化できる
- 顧客の感情を分析する
- 進捗状況と成約率の見える化
- トップセールスのノウハウを共有する
- KPIを定量的に管理できる
- 商談の振り返りとネクストアクションの提案
- 他ツールやシステムとの連携
商談内容をテキスト化する
商談分析に使用するツールに「文字起こし機能」が搭載されていれば、商談内容をテキスト化できます。
商談内容を見える化すれば、商談中には気づかなかった課題や自身の強みに気づけることもあるでしょう。
特定のキーワードから商談の一部を抜粋したり、テーマに沿って商談の振り返りをしたりなどにも活用できます。
コンプライアンスを強化できる
テキスト化した商談内容は、データとして自動で保存されます。
たとえば、顧客との関係性を構築できていない初期の段階では、認識のズレから「言った言わない」などのトラブルが生じるケースもあります。
こうしたトラブルが起きても、ツールに保存されている商談内容を確認すれば、適切な対応が可能です。
トラブルの原因を教訓として活かすことで、コンプライアンスを強化できます。
顧客の感情を分析する
AIが搭載されているツールは、顧客の感情を分析できます。
NLP(自然言語処理)により、商談では気付けなかった顧客の感情を把握できれば、顧客ごとに最適な提案を準備できるでしょう。
ネガティブな感情を抱いた要素を避けて、ポジティブな感情を把握できれば、顧客ニーズにマッチした戦略の立案にも活かせます。
進捗状況と成約率の見える化
商談分析にツールを活用すれば、進捗状況と成約率を見える化できます。
進捗状況や成約率は数字やテキストでも管理できますが、件数が多く内容が複雑になるほど視認性が低下するのが課題です。
進捗状況や成約率をグラフで表示すれば、視認性が向上します。
このように進捗状況や成約率を見える化すれば、管理者が組織全体を管理したいときにも役立つでしょう。
トップセールスのノウハウを共有する
商談分析結果は、トップセールスのノウハウを共有したいときにも役立ちます。
トップセールスの成功事例を元にトークパターンを分析すれば、成約につながりやすいトーク術を活用できるでしょう。
マニュアル化すれば、トークスキルに乏しいスタッフにもナレッジを共有できます。
KPIを定量的に管理できる
商談分析ツールのモニタリング機能を活用すれば、KPIを定量的に管理できます。
管理者が営業担当者からの報告を待つスタイルでは、問題が生じたとき迅速に対応できません。
商談分析ツールを活用すれば、管理者が現場にいなくても問題が生じたプロセスを把握できるので、早期発見と対応を可能にします。
商談の振り返りとネクストアクションの提案
商談の振り返りと、ネクストアクションの提案も可能です。
AIが商談内容を元にネクストアクションを提案するので、方針の変更が必要になっても適切に対応できます。
適切なネクストアクションを把握できれば、成約率の向上が見込めるでしょう。
他ツールやシステムとの連携
他ツールやシステムとの連携もできます。
ツールによって連携できるシステムは異なりますが、既存システムとの互換性の高いツールならスムーズな連携が可能です。
たとえば、CRM(顧客関係管理)と連携すれば、商談内容と顧客情報を紐づけて管理できます。
他ツールやシステムにも活動ログがデータとして記録されるので、さまざまな用途に活用できるのもメリットです。
商談分析のメリット
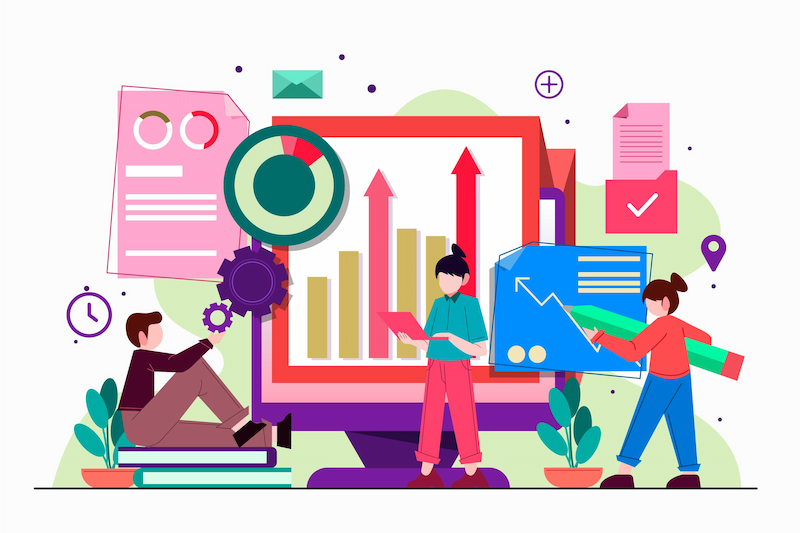
商談分析をするメリットは、以下の3つです。
- 商談スキルを可視化できる
- データを研修や教育に活用できる
- 外部連携により営業力を強化できる
商談内容をテキスト化すれば、自分では気づかない商談スキルを可視化できます。
ツールに蓄積されたデータは、研修や教育にも活用が可能です。社内に蓄積されたデータを活用すれば、教育コストの削減にもつながります。
外部システムと連携すればできることが増えるので、営業力を強化できるのは組織にとっても大きなメリットになるでしょう。
商談分析のデメリット

商談分析には、以下のデメリットも存在します。
- ITリテラシーが求められる
- ツールが増えることで導入コストがかかる
- 社内からの理解を得る必要がある
ツールの活用を前提としている場合は、ITリテラシーが求められます。
外部システムやツールと連携が必要な場合は、ツールが増えた分の導入コストがかかることに留意しましょう。
これまでアナログで対応してきた企業では、ツールによる商談分析に抵抗を持つスタッフが存在するケースがあります。
社内からの理解を得ないまま導入すると、現場が混乱する恐れがあるので理解を得ることも大切です。
商談分析の手法は3種類

商談分析の手法は、以下の3種類です。
- 動向分析
- 要因分析
- 検証分析
それぞれ詳しく見ていきましょう。
動向分析
動向分析は、市場の動向からトレンドや消費者ニーズの変化を予測する手法です。
- 市場規模
- 市場占有率
- 季節によるニーズの変化
- 競合他社の状況
このように、市場のトレンドや消費者ニーズを正確に予測できれば、競合他社との差別化を図れるので、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。
要因分析
要因分析は、自社の営業データから業績が変動した要因を特定する手法です。
例えば、前年度よりも売上が低迷している場合は、どこに要因があるかを特定できます。このケースでは、営業力の低さや市場環境の変化などが要因と考えられます。
要因を特定できれば、具体的な改善策を策定できるのがメリットです。
検証分析
検証分析は、過去の営業データや、動向分析・要因分析の結果を元に効果を検証する手法です。
データに基づき客観的に評価できるので、精度の高い分析ができます。
仮説立てをしてから検証することでナレッジが蓄積されるため、営業力の強化にもつながるでしょう。
商談分析に役立つフレームワーク5選

続いて、商談分析に役立つフレームワークを5つ紹介します。
- 3C分析
- SWOT分析
- PEST分析
- 4P分析
- MEDDIC
3C分析
3C分析は、3つの視点から市場環境を分析するフレームワークです。
- Customer(市場と顧客)
- Competitor(競合ポジション)
- Company(自社の状況)
「Customer」は市場と顧客ニーズや購買プロセスを、「Competitor」は、競合のポジションや商材の特徴を分析します。
顧客と競合の分析結果を元に「Company」で自社の立ち位置を客観的に把握して、最適な戦略を立案します。
SWOT分析
SWOT分析とは、内部環境と外部環境から自社の強みと弱みを割り出すフレームワークです。
- Strength(強み):内部環境
- Weakness(弱み):内部環境
- Opportunity(機会):外部環境
- Threat(脅威):外部環境
内部環境は社内で商品やサービスに影響を与える要因を指しています。
外部環境は、市場や競合など社外で自社商品やサービスに与える影響です。
SWOT分析により自社が置かれる現状を把握できれば、適切なマーケティング施策を立案できます。
PEST分析
PEST分析は、4つの視点から外部環境を分析するフレームワークです。
- Politics(政治):国内政策や法律
- Economics(経済):景気動向や金利変動
- Society(社会):環境問題や生活の変化
- Technology(技術)・技術革新や投資動向
目まぐるしく変化する市場や消費者ニーズを把握するには、マクロな視点で自社を取り巻く環境を分析する必要があります。
4P分析
4P分析は、4つの視点から自社商材をメインに分析するフレームワークです。
- Product(製品・サービス):自社商材の強み
- Price(価格):自社商材の価格
- Place(流通):自社商材を販売するチャネル
- Promotion(プロモーション):自社商材の宣伝や広告
主に、具体的な戦略を立案するマーケティングで用いられます。
4P分析は、4つの要素がそれぞれ関連しているため、バランスを考えながら分析するのがポイントです。
MEDDIC
MEDDICは、6つの視点から受注の確度を分析するフレームワークです。
- Metrics(測定指標)
- Economic Buyer(決裁権者)
- Decision Criteria(意思決定基準)
- Decision Process(意思決定プロセス)
- Identify Pain(課題)
- Champion(擁護者)
6つの要素を分析することで、成約に至るプロセスを見える化できます。
進捗状況や案件情報を見える化して把握しやすくなり、管理者が全体を俯瞰しながら管理できるのがメリットです。
MEDDICは、失注の原因を洗い出して、適切な対策を策定するときにも役立ちます。
商談分析に活用したいツール・システム4選

では最後に、商談分析に活用できるツールとシステムを4つ紹介します。
- SFAツール
- BIツール
- Excel・スプレッドシート
- DSR(デジタルセールスルーム)
SFAツール
SFA(Sales Force Automationツールは、営業支援システムとも呼ばれています。
チームの進捗状況を見える化して共有すれば、属人化を防げるのもメリットです。
営業活動を一元管理できるので、煩雑化しやすい営業活動の業務効率化や生産性の向上につながります。
こちらの記事では、SFAツールについて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
営業支援ツール(SFA)とは?導入するメリットと選ぶ際の注意点まで解説!
BIツール
BI(Business Intelligence Tool)は、企業が管理するあらゆるデータを活用して意思決定をサポートするツールです。
BIツールを活用すれば、データに基づく精度の高い意思決定が可能になります。
膨大なデータの分析やレポート作成などの業務を自動化できるので、業務効率化やコスト削減につながるのもメリットです。
こちらの記事では、BIツールについて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
BIツールとは?おすすめ10選の比較と活用例・基本機能をわかりやすく解説
Excel・スプレッドシート
Excelやスプレッドシートは、無料で利用できるため導入コストをおさえたいときにおすすめです。
Excelは共同編集やデータの共有が限定的なため、スムーズに共有したいなら同時編集やリアルタイムで更新されるスプレッドシートを選ぶとよいでしょう。
DSR(デジタルセールスルーム)
DSR(デジタルセールスルーム)は、BtoB企業向けのオンラインスペースです。
リアルタイムでのチャットや資料共有が可能なので、顧客とスムーズに情報を共有できます。
活動ログが記録されるため、商談分析にも活用が可能です。
まとめ:商談分析を実践して組織としての営業力を強化しよう

商談分析は、商談の振り返りをすることで、商談中には気付けなかった課題を洗い出せます。
解決すべき課題が明確になれば、自ずと解決策も見えてくるでしょう。
業務効率化やチーム利金簿強化につながるのもメリットです。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、商談分析を実施して組織としての営業力を強化して成果につなげてください。