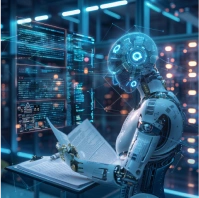販路拡大とは?16個の手法や戦略の立て方・補助金制度も紹介

企業が利益を得て成長し続けるには、経営の安定化が何よりも欠かせません。
しかし、事業が軌道に乗っても販路が限定されると、変化が激しい市場動向や顧客行動の変化に追いつけなくなり、売上の低迷を招く恐れがあります。
こうしたリスクを回避するには、販路拡大を検討しなければなりません。
とはいえ、販路拡大の手法はさまざまあるため、自社に合う手法が分からず悩むこともあるでしょう。
そこで本記事では、販路拡大の手法を16個紹介します。戦略の立て方や実施する手順、補助金制度についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
販路拡大とは?

販路とは、企業が扱う商品やサービスを販売するルートのことです。
販路拡大は、既存ルートをベースに、さまざまな手法やチャネルを駆使して新規顧客や取引先を増やし、売上を増加させる戦略を指します。
たとえば、地域限定で提供していた商品やサービスの場合では、対象エリアを近隣または全国に広げ売上アップを目指すのが販路拡大です。
販路拡大と販路開拓の違い

販路拡大は「既存の自社サービスや商品の売上を増やす」ことであり、販路開拓は「新たなルートを作り新規顧客を獲得する」のが目的です。
販路拡大においては、既存ルートで人員や予算を拡充し売上増加を目指します。
販路開拓は、新たなルートを開拓する必要があるため、プロセスが大きく異なります。
販路拡大の重要性

販路を確立しても、継続的に売れるとは限りません。
販路開拓後しばらくは順調に売上が伸びていても、市場の飽和や顧客行動の変化により顧客獲得が頭打ちになれば、売上の低迷を招く恐れがあります。
企業が5年先・10年先にも生き残り成長し続けるには、販路拡大が必要不可欠です。
また、既存の販路で売上が出ているなら、拡大によりさらなる売上増加が見込めるというメリットもあります。
販路拡大に関わる3つのチャネル

販路は、下記の3つのチャネルで構成されています。
- コミュニケーションチャネル
- 流通チャネル
- 販売チャネル
コミュニケーションチャネルは、企業が消費者に対して情報を発信したり、消費者が企業に対して問い合わせをしたりするのに活用します。
流通チャネルは、企業が消費者に商品やサービスを届けるために欠かせない、物流・卸売・小売などの業者が介在するチャネルです。
販売チャネルは、企業が消費者に商品やサービスを販売する、実店舗やECサイトなどを指します。
いずれも販路拡大には重要なチャネルであり、物・お金・情報の流れにも関わっています。
販路拡大のオンライン手法

では次に、販路拡大のオンライン手法を9つ紹介します。
- ECモールに出店する
- SNSで情報を発信する
- オウンドメディアを運営する
- メルマガを配信する
- 広告を出稿する
- 口コミサイトに登録する
- パブリシティを活用する
- リファラルマーケティングを活用する
- マッチングサービスを利用する
ECモールに出店する
ECモールは、オンラインで利用できるショッピングモールのことです。
出店者は店舗を構える必要がないためコストを削減でき、利用者は場所を問わず気軽に買い物ができます。双方にメリットがあり、集客力が高いのも特徴です。
ただし、競合他社に埋没しやすいことに留意しましょう。
差別化を測るためには、効果的なプロモーションや自社の強みを活かした戦略の立案など工夫が必要です。
SNSで情報を発信する
SNSは若年層に人気があるので、20代~30代のターゲットにアプローチしたい場合に有効です。
情報拡散力に優れていることから、企業のブランディングや認知拡大効果が期待できます。幅広い層にアプローチでき、興味を持ったユーザーと接点を持てるのもメリットです。
また、ターゲティング精度の高いSNS広告の活用も可能であり、ローコストで運営できるという特徴もあります。
オウンドメディアを運営する
オウンドメディアは、自社サイトやブログなどで、ユーザーに有益な情報を発信できるのが強みです。
ユーザーにサイトやブログを訪問してもらうには、SEO対策が欠かせません。しかし、検索上位に表示されれば多くのファンを獲得できる可能性があります。
また、サイトを訪問するだけでなく、自ら資料請求や問い合わせといったアクションを起こすなど、見込み角度の高い顧客を獲得できるのもメリットです。
メルマガを配信する
SNSは若年層に有効な手法として紹介しましたが、高年層へのアプローチも含めて、メルマガも有効です。定期配信することで、顧客と長期的な関係性を構築できます。
発信側も受信側も、都合の良いタイミングで送受信でき、多くの情報を伝えたい時にも活用できます。
ただし、開封してもらえなければ意味がありません。「興味を引く件名を付ける」「開封してもらいやすい時間帯に送信する」といった工夫が必要です。
広告を出稿する
オンライン広告にはさまざまな種類がありますが、多くのユーザーにアピールできる手法です。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| リスティング広告 | 検索キーワードに連動して表示される |
| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリの広告枠に表示される |
| 動画広告 | 映像と音声で訴求できる |
| 純広告 | 特定メディアの広告枠を買い取り一定期間表示される |
| SNS広告 | SNS上で配信される |
| アフィリエイト広告 | クリックや購入など所定の条件を満たすと報酬が発生する |
| ネイティブ広告 | コンテンツに融合して違和感なく表示される |
このように、広告によって特徴や期待できる効果は異なります。また、費用もそれぞれ異なるので、目的や予算と照らし合わせながら選ぶ必要があります。
口コミサイトに登録する
口コミは、実際に商品やサービスを利用したユーザーが感想や使用感を書き込むので、購入前の参考になります。
ただし、すべてのユーザーが口コミを書くとは限らないため、書いてもらう工夫が必要です。
- 店頭販売で商品を手渡す際に直接依頼する
- フォローメールで依頼する
- QRコードを用意する
- 口コミを条件にクーポンを配布する
このように、口コミを書いてもらえるように誘導するのも有効です。
ただし、良い口コミを書くように強制すると悪い印象を与えるので注意してください。
また、中には悪い口コミが書き込まれる場合もありますが、放置せず丁寧なフォローアップで信頼回復を図ることも大切です。
パブリシティを活用する
パブリシティとは、メディアに取り上げてもらい情報を発信する手法です。
記者会見やインタビュー、プレスリリースやPROイベントなどを通じてアプローチすれば、認知を拡大しやすくなります。
多くのユーザーにアプローチできる点では、広告に通じるものがありますが、パブリシティはメディアが積極的に宣伝するのでコスト削減が可能です。
媒体による違いはあるものの、客観的な視点で発信された情報は、信頼性が高いと判断されます。
リファラルマーケティングを活用する
リファラルマーケティングは、既存顧客や取引先から顧客を紹介してもらう手法です。
既存顧客や取引先の担当者とはすでに接点を持っており、ある程度関係性も構築されています。
信頼できる企業という理解を得られている状態なので、成果につながりやすいのも特徴です。
なお、リファラルマーケティングを活用する際は、紹介者にインセンティブを用意しておくとよいでしょう。
マッチングサービスを利用する
効果的かつ短期間で販路拡大を目指すなら、マッチングサービスの利用も選択肢に入ります。
たとえば、特定の業界に特化したビジネスマッチングサービスなら、自社のニーズに合うパートナーを見つけやすくなります。
商談の機会を得られても、その後のプロセスは自社で対応する必要があること、必ず理想のパートナーが見つかるとは限らないことに留意しましょう。
販路拡大のオフライン手法

では次に、販路拡大のオフライン手法を7つ紹介します。
- テレアポによるアプローチ
- ダイレクトメールを送る
- 飛び込み営業でアプローチする
- 展示会・イベントに参加する
- セミナー・ウェビナーを開催する
- 手紙
- はがき・FAXの送付
テレアポによるアプローチ
テレアポは、電話で見込み顧客にアプローチしてアポイントを獲得する手法です。
短期間で多くの見込み顧客にアプローチでき、トークスクリプトを活用すれば応対品質を標準化できるといったメリットもあります。
顔が見えない電話での対応となるため、担当者に高度なスキルが求められるのが懸念点ですが、自社での対応が困難な場合は、テレアポ代行を検討するとよいでしょう。
ダイレクトメールを送る
ダイレクトメールは、顧客に直接アプローチできます。
ただし、開封してもらえなければ意味がありません。1日に何通ものダイレクトメールを受け取るような場合には、差別化を図る工夫が必要です。
- 大きい封筒を使用する
- 立体形状の封筒を使用する
- ノベルティを同封する
このように、他のダイレクトメールに埋もれないような工夫を取り入れれば、開封率を高められます。
また、開封に手間がかかると面倒になり、中身を見てもらえない恐れがあるので、開封しやすいことも重要です。
飛び込み営業でアプローチする
飛び込み営業は、事前のアポイントなしで顧客先を訪問する手法です。
移動時間や交通費がかかる他にも、突然訪問しても取り合ってもらえないなどのデメリットもありますが、相手の反応に応じて臨機応変に対応できます。
新型コロナウイルスの影響で実施する企業は少なくなっていますが、対面対応を重要視する顧客には有効な手段です。
展示会・イベントに参加する
展示会やイベントは、角度の高い見込み顧客に出会える可能性が高い手法です。
そもそも、展示会やイベントに足を運ぶ顧客は、自社業界や商材に関心が高い可能性があります。
もちろん競合他社も多く出展しているので、自社ブースに足を運んでもらう工夫が欠かせません。
その場で商談のアポイントを獲得できなくても、名刺交換をしておけば後日アプローチのきっかけを作れます。
セミナー・ウェビナーを開催する
セミナーに足を運ぶ顧客も、見込み角度が高いと考えられます。対面で有益な情報を提供できるので、顧客満足度の向上につながります。
セミナー終了後に懇談会を開催すれば、顧客との心理的な距離が縮まり関係性を構築しやすくなるのもメリットです。
なお、セミナーに参加できない可能性もあるため、場所を選ばず参加できるウェビナーも検討するとよいでしょう。
手紙
手紙は、ダイレクトメールよりもピンポイントでアプローチできます。
たとえば、大企業の経営者のように普段は接点を持てない相手でも、手紙なら本人に直接届くので開封してもらえる可能性があります。
ただし、印刷した文字だとダイレクトメールと間違われる可能性があるので、手書きで書くのもポイントです。
なお、手書きに自信がない場合は、代筆サービスを利用する手もあります。
はがき・FAXの送付
はがきやFAXは、ダイレクトメールの一種ですが、内容をすぐに確認できるのが特徴です。
開封する手間がないため、忙しい方でも目に留まれば記憶に残りやすくなります。
すぐに行動には移さなくても、保管できるので後から問い合わせや資料請求につながる可能性があるのもメリットです。
販路拡大にはO2Oマーケティングも有効

O2O(Online to Offline)マーケティングとは、オンラインとオフラインを併用する施策です。
たとえば、実店舗だけでは思うように売上が伸びない時に、アプリやオンラインショップと連携すれば、より多くの顧客にアプローチできます。
アプリでクーポンを発行したり、オンラインショップから在庫を確認してお取り置き依頼をしたりといった使い方も可能です。
O2Oマーケティングにより、多くの顧客にアプローチできれば売上向上にもつながるでしょう。
販路拡大のメリット

続いて、販路拡大のメリットを3つ紹介します。
- 売上の増加が見込める
- 競合他社との差別化を図れる
- リスクを分散できる
売上の増加が見込める
売上の増加が見込めるのは、企業にとって大きなメリットです。
現状の販路で成果が出ていても、販路が限定されると外部環境の影響を受けた時に、売上が低迷すれば企業の存続が危ぶまれる恐れがあります。
そこで、販路拡大によりリーチを増やせれば、収益の多角化により経営が安定します。
競合他社との差別化を図れる
販路拡大により売上が増加すれば、市場シェアの拡大も可能です。
市場シェアの拡大で自社の優位性を確立できれば、競合他社との差別化を図れます。
特に、競争が激しい業界や商材においては、優位性をアピールして顧客に選ばれやすくなるといったメリットもあります。
リスクを分散できる
そして、リスクを分散できるのもメリットです。
販路が限定されると、市場動向や経済状況の影響を受けて販路が絶たれた場合に、事業を継続できなくなる恐れがあります。
販路拡大で複数のチャネルを持っていれば、どこかのチャネルが影響を受けても他のチャネルで対応できます。
販路拡大を効果的に実施する手順4ステップ

それでは、販路拡大を効果的に実施する手順を、4つのステップに分けて紹介します。
- 入念に市場調査や分析を行う
- ターゲットを明確にする
- ターゲットにマッチした販路を決定する
- 継続的に評価と改善をする
ステップ1.入念に市場調査や分析を行う
まず、入念に市場調査と分析を行います。
闇雲に販路拡大を目指しても、ターゲットのニーズにマッチしていなければ購入してもらえません。
市場調査では、ターゲットのニーズや競合他社の情報、購買傾向などの情報を収集・分析します。
分析によりターゲットのニーズや購買傾向を把握できれば、適切な販路を見出せるでしょう。
ステップ2.ターゲットを明確にする
ターゲットを明確にするのも重要な施策です。
そもそも、ターゲットが曖昧だとニーズにマッチした戦略を立案できません。良質な商品やサービスでも、ニーズにマッチしていなければ使いたいとは思ってもらえないでしょう。
ターゲットを明確にするには、ペルソナ設定が有効です。
ターゲットが複数に及ぶ場合は、ターゲットごとにペルソナも複数設定してください。
ステップ3.ターゲットにマッチした販路を決定する
ターゲットを明確化したら、ニーズにマッチした販路を決定します。
たとえば、若年層にはSNSが有効ですが、SNSだけで成果が出るとは限りません。
見込み角度が高いと判断できたら、メルマガやダイレクトメールなどを活用したO2Oマーケティングも検討しましょう。
ターゲットによって適切な販路は異なるため、ニーズに合わせた見極めも重要です。
ステップ4.継続的に評価と改善をする
販路拡大を実行しても、そこで終わりではありません。
ターゲットにマッチした販路を決定しても、成果が出ていないなら戦略の見直しが必要です。
そこで、実行後の継続的に評価と改善を繰り返せば、課題に対して適切に対応と改善ができます。
評価と改善には、PDCAサイクルを回すとよいでしょう。
- Plan(計画)
- Do(実行)
- Check(評価)
- Action(改善)
PDCAサイクルは、業務改善に役立つフレームワークです。
なお、PDCAサイクルのスパンが長いと、課題の発見と対応が遅れ業務に支障が出る恐れがあります。1週間や10日など、できるだけ短いスパンで回していくことが重要です。
販路拡大に向けて活用できる補助金制度

販路拡大を実現すれば売上の増加が見込めますが、一定のコストがかかるのが懸念点です。
資金不足で販路拡大が難しい場合は、補助金制度を利用する選択肢があります。
販路拡大に向けて活用できる補助金制度を紹介します。
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を支援する制度です。
| 対象 | 下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人 従業員数5人以下の商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 従業員数20人以下の宿泊業・娯楽業 従業員数20人以下の製造業その他 |
|---|---|
| 補助率・補助上限額 | 補助率:2/3補助上限額:200万円 |
| 対象経費 | 機械装置等 広報費 ウェブサイト関連費 展示会等出展費 販路開拓に伴う旅費 開発費 資料購入費 雑役務費 借料設備 処分費 委託・外注費 |
ただし、小規模事業者持続化補助金には期限があるため、随時利用できるわけではないことに留意しましょう。
スケジュールについては、公式サイトで確認してみてください。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新市場への進出や事業再編など、事業の再構築に意欲を有する中小企業を支援する制度です。
| 対象 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%※以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~4%※以上増加の達成 ※事業類型により異なる |
|---|---|
| 公募内容(第13回の場合) | 補助上限通常類型:3,000万円 GX進出類型:5,000万~1億円 コロナ回復加速型:1,500万円 |
| 補助率 | 中小企業:1/2 ※コロナ回復加速化枠3/4 中堅企業:1/3 ※コロナ回復加速化枠2/3 |
| 対象経費 | 建物費 機械装置・ システム構築費 技術導入費 専門家経費 運搬費 クラウドサービス利用費 外注費 知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費 研修費 廃業費 |
事業再構築補助金は、応募後に採択された場合に支給されます。
また、申請には必要書類をすべて揃える必要があり、採択後には「事業化状況報告」「実績報告書」などの提出が義務付けられていることに留意しましょう。
スケジュールも事業類型によって異なり、期限内の申し込みが必須です。詳細は公式サイトより確認してみてください。
テレアポによる販路拡大・開拓ならディグロス

テレアポは直接顧客の声を聞き反応を確認できる反面、アポ獲得率が低いのが懸念点です。
自社対応で成果が出ない場合は、1,600社以上の支援実績を持つ株式会社ディグロスにお任せください。
弊社では、お客様のご要望に沿った形で、アポイントメント(商談の場)をセッティングします。
アポイントメント獲得を成果点として、件数ごとに単価を設定する成果報酬型なので、低リスク・低コストでご利用いただけます。
テレアポによる販路拡大・開拓をご検討中の企業様には、電話やメールで説明しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:自社に合う方法で販路拡大を成功させよう

販路拡大で売上が増えれば、企業の経営は安定します。
販路拡大の手法は、企業が抱える課題や目標によって適切な手法は異なりますが、O2Oマーケティングにより効果的に実施できるのもメリットです。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、自社に合う方法で販路拡大を成功させて売上アップを目指してください。