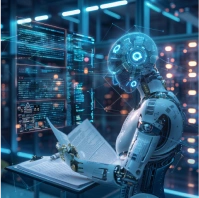リードナーチャリングとは?施策10選や成果につなげるコツも紹介

マーケティングで多くのリード(見込み顧客)を獲得しても、成約につながらなければ売上にはつながりません。
リード獲得後は、見込み顧客との関係性を構築しながら成約につなげるリードナーチャリングが重要です。見込み顧客ごとに、購買意欲の度合いは異なるからです。
しかし、リードナーチャリングにはさまざまな施策があるため、具体的に何をすればいいか迷うこともあるでしょう。
そこで本記事では、リードナーチャリングの施策10選を紹介します。実施する手順や成果につなげるコツについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
リードナーチャリングとは?

リードとは見込み顧客を指し、ナーチャリングは育成の意味を持ちます。リードナーチャリングとは、見込み顧客を育成して成約につなげるプロセスのことです。
リードとして獲得した時点では「購買意欲が低い」「自社商材への関心が低い」というケースも少なくありません。
そこで、見込み顧客にさまざまな方法でアプローチしながら、課題やニーズを正しく把握できれば見込み顧客を納得させる提案を導き出せます。
最適な提案を提示されれば購買意欲が高まり、見込み顧客から顧客へ転換しやすくなるでしょう。
ナーチャリングとリードナーチャリングとの違い

ナーチャリングとリードナーチャリングは、どちらも意味合いは同じですが、対象が異なります。
- ナーチャリング:顧客育成
- リードナーチャリング:見込み顧客の育成
いずれも育成を目的とした活動を行いますが、ナーチャリングには新規顧客だけでなく、既存顧客も含まれます。
たとえば、成約を獲得しても一度きりというケースもあるでしょう。そこで、既存顧客に対してナーチャリングを実施すれば、リピーターを獲得できる可能性があります。
既存顧客とはすでに接点があり関係性も構築できているので、リピーターに転換できればアップセルやクロスセルによる利益拡大も見込めます。
リードナーチャリングの対象は、新規顧客のためリード獲得のコストがかかるものの、結果的に顧客の母数がふえれば将来的な売上拡大につながるでしょう。
リードナーチャリングが重要視される背景

それでは、リードナーチャリングが重要視される背景を、3つの視点から紐解いていきます。
- ユーザー行動の変化に対応するため
- 各ユーザーに適切な情報提供する必要があるため
- 受注確度が高いユーザーに営業リソースを集中させるため
ユーザー行動の変化に対応するため
まず、ユーザー行動の変化に対応する必要性です。
近年、インターネットの普及に伴い、ユーザーは欲しい情報を手軽に入手できます。そのため、企業が一方的に情報を発信するスタイルでは、見込み顧客を獲得しづらくなっています。
そこで、企業がユーザーに先立ってアプローチするためにも、リードナーチャリングは必要不可欠です。
各ユーザーに適切な情報提供する必要があるため
これまでは、企業がWebサイトや広告でユーザーに情報を発信していました。
しかし、現在は情報の発信・入手チャネルが多様化しているため、チャネルが限定されると各ユーザーに適切な情報を提供できません。
リードナーチャリングでは、顧客ごとの情報を分析して課題やニーズを洗い出すので、パーソナライズされたアプローチが可能です。
受注確度が高いユーザーに営業リソースを集中させるため
成約率を高めるには、受注確度の高いユーザーへのアプローチが不可欠です。
受注確度が低いユーザーへの対応に時間を費やしても、成果につながらなければ営業活動の労力を無駄にする恐れがあります。
その間に、受注確度の高いユーザーへの対応が遅れると、機会損失を起こしかねません。
そこで、受注確度の高いユーザーに営業リソースを集中させれば、営業活動の最大化により受注率の向上が見込めます。
リードナーチャリングの施策10選

では次に、リードナーチャリングの施策10選を紹介します。
- テレマーケティング
- インサイドセールス
- メールマーケティング
- オウンドメディア
- セミナー・イベント
- SNS
- リターゲティング広告
- Webトラッキング
- ホワイトペーパー
- ダイレクトメール
テレマーケティング
テレマーケティングは、電話で見込み顧客と関係性を構築する手法です。
顧客先への移動が不要なため、多くのリードにアプローチでき、これまで訪問が難しかったエリアにも対応できます。
移動時間や交通費を節約できる反面、相手の表情が見えないため、担当者には声のコミュニケーションスキルが求められます。
インサイドセールス
インサイドセールスは、電話やメール・Web会議ツールなどを活用する、非対面の営業手法です。
- 分業型:マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールス
- 独立型:インサイドセールスが一貫担当
このように、分業のタイプで役割は異なるものの、各部門・担当者が専門性を発揮できるのがメリットです。
また、新たにインサイドセールスを導入する場合は、大幅な組織改革が必要になることに留意しましょう。
メールマーケティング
メールマーケティングは、メルマガやステップメールなど、ターゲットに合わせてメールを配信する手法です。
定期的に配信するメルマガは、顧客と長期的に関係性を構築できます。一度に多くの情報を提供でき、かつ最新情報を発信できるのもメリットです。
ステップメールは、事前に設定したシナリオに基づき、ユーザーが特定の行動を起こしたタイミングで自動発信されます。
- 資料請求やお問い合せ直後のお礼メール
- 2~3日後にお役立ち情報を提供
- 1週間前後で商材の紹介メール
- 2週間後に限定キャンペーンの案内メール
上記はあくまでも一例ですが、自動で段階的なアプローチを実現できます。
オウンドメディア
オウンドメディアは、自社が運営するメディアで情報を発信する手法です。
| 種類 | コンテンツ |
|---|---|
| 公式サイト | 企業紹介 自社商材紹介 ニュース ブログ 事例・実績紹介 資料請求 お問い合わせ・FAQなど |
| 独立型 | 公式サイトとは別に、自社商材に関連する情報を自由なスタイルで発信する媒体 自社商品関連の情報 見込み顧客へ向けた情報 |
オウンドメディアでは、ユーザーに有益な情報を提供することが大切です。また、定期的に更新して、最新情報を発信するなどの工夫も必要です。
また、オウンドメディアを適切に管理・運営すれば、長期的に情報を発信できます。
セミナー・イベント
セミナーやイベントは、自社商材に高い関心や興味を持つターゲットを獲得できます。
ターゲットに合わせて適切なテーマを設定する必要がありますが、ホットリード(受注確度の高い見込み顧客)との接点を持てるのは大きなメリットです。
その場で商談につながらなくても、名刺を交換しておけば、後日アプローチのきっかけを作れます。
近年では、会場に足を運ばずに済むことから、参加へのハードルが低いウェビナーを開催する企業も増えています。
SNS
SNSは、情報拡散力に優れた手法です。
企業が発信する情報に対して、ユーザーはフォローやコメントなどで、気軽にコミュニケーションを図れます。
違和感なく広告を表示させたり、キャンペーン情報などを発信したりでき、オウンドメディアに誘導しやすいのもメリットです。
リターゲティング広告
リターゲティング広告は、過去に自社のWebサイトを訪問したユーザーに対して、広告を配信する手法です。
ターゲットは、すでに企業名や商材名を認知しているため、休眠顧客の掘り起こしに有効な施策としても知られています。
ただし、過度な訴求は不快にする恐れがあるので、表示回数を調整するなどの工夫を取り入れるとよいでしょう。
Webトラッキング
Webトラッキングは、ユーザー行動を分析して、課題やニーズを見える化する施策です。
Cookieを元に情報を収集するため、流入経路や関心や興味のあるコンテンツの把握に役立ちます。
Webトラッキングの情報を元にスコアリングすれば、ホットリードを見極めやすくなるでしょう。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、見込み顧客にとって関心や興味が高いと思われる内容をまとめた資料のことです。自社サイトのダウンロードフォームから入手できます。
たとえば、「事例をまとめた資料」「商材に関するお役立ち情報やノウハウを記載した資料」などが該当します。
見込み顧客に有益な情報を提供でき、ダウンロードの際に入力するメールアドレスや個人情報を入手できるのもメリットです。
ダイレクトメール
ダイレクトメールは、紙媒体でアプローチする手法です。
ターゲットに直接届けられ、開封後も保管してもらえれば、後日ダイレクトメールから問い合わせや資料請求につながる可能性があります。
ただし、開封してもらえなければ意味がありません。封筒のサイズや質感、読みたくなるキャッチコピーなど、他のダイレクトメールと差別化を図ることが大切です。
リードナーチャリングを実施する4つのメリット

では次に、リードナーチャリングを実施するメリットを4つ紹介します。
- 長期的に顧客をフォローする仕組みを構築できる
- 見込み客の離脱を防いで費用対効果を高められる
- 休眠顧客の掘り起こしにつながる
- 業務効率化につながる
長期的に顧客をフォローする仕組みを構築できる
まず、長期的に顧客をフォローする仕組みを構築できるのは、大きなメリットです。
インターネットの普及に伴う消費者行動の多様化により、購買プロセスの長期化という新たな課題も発生しています。
自社商材に関心や興味があっても、検討期間中に適切なフォローができなければ、競合他社に乗り換えられるかもしれません。
そこで、リードナーチャリングを実施して、長期的にフォローすれば自社商材を選んでもらえる可能性が高まります。
見込み客の離脱を防いで費用対効果を高められる
成約につなげるには、受注確度の高い見込み顧客に対して優先的にアプローチするのも不可欠です。
特に、検討期間が6か月~1年と長くなるケースでは、見込み顧客の離脱が起きやすい傾向があります。
リードナーチャリングで適切にフォローしていれば、見込み顧客の離脱を防げるでしょう。
たとえ購入までのプロセスが長い高単価商材でも、リードナーチャリングで成約につなげられます。
休眠顧客の掘り起こしにつながる
リードナーチャリングは、休眠顧客の掘り起こしにもつなげられます。
すでに関係性は構築できているので、一定期間取引がなくても、再アプローチで興味を持ってもらえる可能性はあります。
新規顧客を獲得するよりも効果的に営業活動ができ、コストをおさえられるのもメリットです。
業務効率化につながる
そして、業務効率化につながるというメリットもあります。
顧客情報の分析とスコアリングによって、ホットリードに営業リソースを注力すれば成約につながりやすくなるでしょう。
たとえば、インサイドセールスの分業型では、フィールドセールスに受注確度の高いリードを引き渡せます。
もちろん、部門間の連携や情報共有は必要ですが、成約率の向上によりチームのモチベーションがアップすれば組織力の強化にもつながります。
リードナーチャリングの注意点

リードナーチャリングには、デメリットも存在します。実施する際には、メリットとデメリットの両方を理解することが大切です。
- リソースの確保が求められる
- 一定数以上の見込み顧客を獲得する必要がある
- すぐに成果が出るわけではない
以降でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
リソースの確保が求められる
まず、リソースの確保が求められます。
受注確度の高いリードを選定するには、徹底した分析やスコアリングが欠かせません。さらに、コンテンツの運営と管理にも、人材が必要です。
特に、リードナーチャリングの運用開始直後は、仕組みを構築するためのリソースが欠かせません。
リソースを確保できない場合は、一部の業務をアウトソーシングする選択肢もあります。
一定数以上の見込み顧客を獲得する必要がある
リードナーチャリングの効果を最大化するには、一定数以上の見込み顧客を獲得しなければなりません。
リードを獲得しても、大半がコールドリード(受注確度が低い見込み顧客)では、顧客と関係性を構築するのが難しくなります。
仮に関係性を構築できたとしても、長い時間がかかりその間にホットリードを取りこぼせば、機会損失のリスクが高まります。
また、人材不足が原因で十分なリードを獲得できないと、リードナーチャリングの効果を最大化できません。
リソースの確保が難しい場合は、代行サービスを検討するとよいでしょう。
こちらの記事では、リード獲得代行会社のおすすめを紹介していますので、あわせてご覧ください。
リード獲得代行会社のおすすめ15社【2025年7月】費用相場や選び方も
すぐに成果が出るわけではない
リードナーチャリングは、長期的に顧客と関係性を構築するのが目的です。
導入してすぐに成果が出るわけではありません。
短期間で成果を出す必要がある業種や商材には、不向きとなる場合があることに留意しましょう。
リードナーチャリングを実施する手順8ステップ

では次に、リードナーチャリングを実施する手順を8つのステップに分けて紹介します。
- 目的を明確にする
- 社内体制を整備する
- ペルソナを設定する
- カスタマージャーニーマップを作成する
- フェーズに沿ったコンテンツを作成する
- KPIを設定する
- 施策を決定する
- 実施後も効果測定と改善を繰り返す
ステップ1.目的を明確にする
まず、目的を明確にしてください。
目的が不明瞭では、リードナーチャリングを実施しても成果を正しく評価できません。
- なぜリードナーチャリングを導入するのか
- リードナーチャリングで何を実現したいのか
このように大きな目標を立てたら、さらに細分化することで目的をイメージしやすくなります。
目的が明確化されれば自ずとやるべきことも把握でき、目的に向かいチーム一丸となって行動できます。
ステップ2.社内体制を整備する
次に、社内体制を整備します。
- 戦略の立案
- コンテンツの企画と作成
- リードナーチャリングの実施
このように、リードナーチャリングの実施までには、各フェーズでの準備も不可欠です。
たとえば、インサイドセールスの分業型では、戦略の立案とコンテンツの企画・作成をマーケティング部門が行い、リードナーチャリングをインサイドセールスが行います。
社内体制の整備には、各部門や担当者の役割を明確にするのも重要です。
また、大幅な組織改革が必要な場合は、事前に社内からの理解を得ておく必要もあります。
ステップ3.ペルソナを設定する
そして、ペルソナを設定します。
獲得したリードが自社商材のニーズにマッチしていなければ、労力を注いでも成果にはつながりません。
ペルソナ設定は、架空の人物像を設定してターゲットへの理解を深める目的があります。
| ターゲット | 設定項目 |
|---|---|
| BtoB | 企業の基本情報(会社名・資本金・事業内容・従業員数) 企業情報(社風・経営理念・組織体制) 意思決定に関わる人 担当者(氏名・年齢・性別) 部署・役職 抱えている課題やニーズ 決定権の有無など |
| BtoC | 氏名・年齢・性別 居住地 職業・勤務先 家族構成 趣味・休日の過ごし方 課題・ニーズなど |
上記は一例ですが、項目はできるだけ細かく設定するほど、ターゲットへの理解が深まります。
ターゲットの課題やニーズを正確に把握していれば、リードナーチャリングの効果を最大化できるでしょう。
なお、ターゲットが複数いる場合はペルソナも複数設定するなどの注意が必要です。人物像をイメージしづらい場合は、既存顧客をモデルにしてください。
ステップ4.カスタマージャーニーマップを作成する
次は、ペルソナを元にカスタマージャーニーマップを作成します。
カスタマージャーニーマップとは、見込み顧客が商材を認知してから、購買に至るまでのプロセスを見える化したものです。
各工程には、顧客の行動や感情、タッチポイント(どのような接点があるのか)を設定します。
カスタマージャーニーマップは、顧客の視点で課題やニーズを把握できるので、客観的に分析できるのがメリットです。
ステップ5.フェーズに沿ったコンテンツを作成する
カスタマージャーニーマップで設定したフェーズに基づき、コンテンツを作成しましょう。
たとえば、タッチポイントがセミナーやイベントなら、自社商材への関心や興味は高いと考えられます。メルマガやホワイトペーパーで有益な情報を発信していけば、購買意欲を高められるでしょう。
SNSからの流入なら、SNS広告での訴求やWebサイトへの誘導、ステップメールなども展開できます。
フェーズに沿ってコンテンツを作成すれば、効果的にリードナーチャリングを実施できます。
ステップ6.KPIを設定する
次は、KPI(重要業績評価指標)を設定します。
KPIは、最終目標となるKGI(重要目標達成指標)までのプロセスを把握するための指標であり、KGIから逆算して設定します。
なお、KPIを設定しても、達成できなければ意味がありません。自社の現状と照らし合わせながら、実現可能な数値を設定するのも重要です。
ステップ7.施策を決定する
次に、施策を決定しますが、必ずしも施策が一つとは限りません。
カスタマージャーニーマップに基づき設定すれば、顧客の行動や感情に合わせて有効な施策を設定できるでしょう。
顧客との関係性を構築するには、継続的に有益な情報を発信できる施策であることも重要です。
ステップ8.実施後も効果測定と改善を繰り返す
リードナーチャリングの施策は、実施したら終わりではありません。実施後は、PDCAサイクルを回しながら効果測定と改善を繰り返してください。
入念に準備をして施策を決定しても、それが顧客にとって最適とは限りません。もし成果につながらなくても、失敗した原因が分かれば改善策を見出せます。
なお、PDCAサイクルのスパンが長すぎると、課題の発見と対応が遅れるので、短いスパンで回しましょう。短いスパンで回せば、早期発見と改善が可能です。
リードナーチャリングを成功に導く4つのコツ

リードナーチャリングを成功に導くために、おさえておきたい4つのコツを紹介します。
- ターゲットへの理解を深める
- 顧客情報を一元管理する
- フェーズごとに適切なチャネルでコンテンツを提供する
- 丁寧にフォローアップする
ターゲットへの理解を深める
まず、ターゲットへの理解を深めておきましょう。
自社商材に高い関心や興味を持っていても、成約を獲得するまでの間には検討期間があります。
ターゲットへの理解が足りず、購買意欲が高まっていない状態で提案しても、成約には至らないでしょう。「強引に売りつけた」と誤解を与えると、他社に乗り換えられる恐れがあります。
そこで、ターゲットへの理解を深めておけば、課題やニーズに合わせたアプローチが可能になります。
顧客情報を一元管理する
顧客情報は、一元管理するのも重要です。
担当者や部署が個別に情報を管理すると、必要なときに情報を確認できません。属人化により顧客への対応が遅れると、失注リスクを高める恐れがあります。
顧客情報の管理には、CRM(顧客情報管理)やSFA(営業支援システム)などのツールを活用するとよいでしょう。
情報共有もスムーズになり、効果的にリードナーチャリングを実施できます。
フェーズごとに適切なチャネルでコンテンツを提供する
そして、フェーズごとに適切なチャネルでコンテンツを提供するのも不可欠です。
一口に見込み顧客といっても、購買意欲や受注確度はそれぞれ異なります。
たとえば、情報収取の初期段階の見込み顧客に売り込んでも、押し売りされたと不信感を持たれれば良好な関係性を構築できません。
アプローチする際は、ターゲットがどの段階にいるのかを見極めながら、適切なチャネルでコンテンツを発信してください。
丁寧にフォローアップする
フォローアップは、丁寧かつ適切なタイミングで実施しましょう。
たとえば、資料請求をした顧客は、速やかにコンタクトを取ってください。資料だけでは伝えきれない情報の提供や、疑問を解決できる可能性があります。
丁寧なフォローアップで購買意欲が高まれば、商談や成約までスムーズに進む可能性があります。
リードナーチャリングが目的のテレマーケティング代行ならディグロス

テレマーケティングは、見込み顧客と直接コミュニケーションを図れるので、リードナーチャリングに有効な手法です。
しかし、電話越しの対応は相手の表情や温度感を把握しづらいため、声のコミュニケーションスキルや傾聴力などが求められます。
専門性の高いスキルを持つ人材の確保が難しい場合は、ディグロスにお任せください。
弊社では、BtoC企業を対象とした、テレマーケティング代行サービスを提供しています。
専用のCRMシステムを活用しながら、蓄積したデータを元に最適なアプローチ方法とトークを導き出します。
最短1か月で業務開始が可能ですので、リードナーチャリングが目的のテレマーケティング代行をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:リードナーチャリングは自社に合う施策で効果的に実施しよう

リードナーチャリングは、顧客と良好な関係性を構築して成約につなげる重要なプロセスです。
一口に見込み顧客といっても、受注確度や購買意欲はそれぞれ異なるため、フェーズごとに適切なチャネルとコンテンツを見極める必要があります。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、自社に合うリードナーチャリングの施策を見極めて効果的に実施してください。