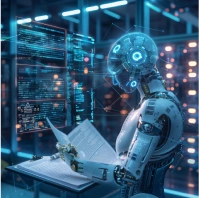インサイドセールスでリードナーチャリングは重要!有効な戦略や方法も紹介

インターネットの普及に伴う顧客行動の変化により、企業が一方的に売り込む営業手法が通用しなくなっています。
インサイドセールスは電話やメールを活用しますが、非対面でもリードナーチャリングを強化することで顧客との関係性を構築できるのがメリットです。
とはいえインサイドセールスにはコツが必要なため、リードを獲得しても成果につながらず悩む企業は少なくありません。このようなケースでは、リードナーチャリングの見直しが必要です。
そこで本記事では、インサイドセールスでリードナーチャリングが重要な理由について解説します。有効な戦略や方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
インサイドセールスのリードナーチャリングとは ?

インサイドセールスは、電話やメールなどを使い非対面で見込み顧客にアプローチして、関係性を構築しながら商談の機会を創出する営業手法です。
リードナーチャリングとは、見込み顧客を育成する施策を指します。
これまでの営業手法ではマーケティング部門が担うのが一般的でした。分業制を前提としたインサイドセールスでは、インサイドセールス部門がリードナーチャリングを担当します。
マーケティング部門が創出した見込み顧客をインサイドセールスが引き継ぎ、関係性を構築しながら商談の機会を創出して、フィールドセールスに引き継ぎます。
フィールドセールスは、インサイドセールスから引き継いだ見込み顧客と商談を行い、受注を獲得するのが役割です。
インサイドセールス部門がリードナーチャリングによって顧客との関係性を構築できていれば、フィールドセールスの成約率向上効果が期待できます。
インサイドセールスにおいてリードナーチャリングが重要視される理由

それでは、インサイドセールスにおいてリードナーチャリングが重要な理由を4つ紹介します。
- 顧客の購買行動が変化している
- 休眠顧客の掘り起こしに有効である
- 成約率の向上が期待できる
- 営業職の人手不足に対応する必要がある
顧客の購買行動が変化している
これまでは、企業が顧客に情報を提供していましたが、インターネットの普及により顧客は、知りたい情報を自由に入手できるようになりました。
たとえば購入を検討している商品やサービスがあった場合でも、顧客は容易に複数社を比較検討できる状態です。すでに意思決定が完了していれば、アプローチしても成約にはつながらないでしょう。
こうした現状に対応するには、意思決定が完了する前に、インサイドセールスのリードナーチャリングを実施して顧客にアプローチする必要があります。
休眠顧客の掘り起こしに有効である
過去に成約を獲得した既存顧客でも、全てがリピーターになるとは限りません。
失注する理由は顧客によって異なるものの、休眠顧客を放置し続ければ競合他社に乗り換えられるリスクが高まります。
インサイドセールスのナーチャリングは、休眠顧客の掘り起こしにも有効です。
数か月や数年の時間が経過していても、関係性を構築できているので、再アプローチによってリピーターを獲得しやすいでしょう。
仮に受注にはつながらなかったとしても、再アプローチでリードナーチャリングを強化すれば商談の機会を創出できる可能性があります。
成約率の向上が期待できる
インサイドセールスでは、見込み顧客との関係性を構築しながら育成できるため、BANTCH情報を活用して成約率の向上が期待できるのも特徴です。
- B(Budget)予算
- A(Authority)決裁権
- N(Needs)要求
- T(Timeframe)検討時期
- C(Competitor)競合
- H(Humanresources)人員体制
BANTCHとは、上記の頭文字から成る情報を指します。
顧客へのヒアリングで得られる情報なので、活用すれば顧客の課題を正確に把握できる他にも、最適なタイミングでアプローチの機会を創出できるでしょう。
最適なタイミングでプローチすれば、成約率の向上が期待できます。
営業職の人手不足に対応する必要がある
近年、少子高齢化や市場の縮小により、多くの企業では人手不足の課題を抱えており、人材の確保には採用の手間や教育費などのコストがかかります。
インサイドセールスは、電話やメールなどを活用して内勤にて営業活動を実施するため、顧客先に出向く必要がありません。
短時間で多くの見込み顧客へのアプローチができるため、限られたリソースでも営業活動を最大化できます。
交通費や採用・人材育成にかかるコストを削減できるのもメリットです。
インサイドセールスにおけるリードナーチャリングのメリットは3つ

では次に、インサイドセールスにおけるリードナーチャリングのメリットを3つ紹介します。
- 確度の高い見込み顧客にアプローチできる
- 潜在顧客をフォローできる
- 属人化を防げる
確度の高い見込み顧客にアプローチできる
一口に見込み顧客といっても、中には潜在層や無関心層が含まれるケースは少なくありません。自社商材に関心が低い顧客にアプローチしても、成約にはつながらないでしょう。
インサイドセールスでは、リードナーチャリングによって顧客との関係性を構築しながら、購買意欲の高い見込み顧客を絞り込みアプローチします。
確度の高い見込み顧客から商談の機会を創出できれば、フィールドセールスの成約率が向上する効果も期待できます。
潜在顧客をフォローできる
インサイドセールスは、潜在顧客をフォローできるのもメリットです。
潜在層は自社商材の存在は知っていても、興味や関心が高いとは限りません。興味や関心が低い状態でアプローチしても、成果にはつながらないでしょう。
そこでインサイドセールスがリードナーチャリングを実施すれば、潜在顧客をフォローできます。
すぐに商談の機会を得られなくても、関係性を構築できれば、必要になったタイミングで顧客からのアプローチにつながる可能性もあります。
属人化を防げる
インサイドセールスにはツールの活用と、部門間の連携を強化するために情報を共有する体制の整備が欠かせません。
目的によって導入するツールは異なるものの、ツールには活動ログを記録できます。ツールに蓄積されたデータや情報を社内で共有すれば、属人化を防げます。
属人化の解消は、部門間の連携を強化できるので、成約率の向上にもつながりやすくなります。結果として売上が上がれば、企業の成長にもつながるでしょう。
インサイドセールスで用いられるリードナーチャリングの手法

続いて、インサイドセールスで用いられる、リードナーチャリングの手法を6つ紹介します。
- テレマーケティング
- メールマーケティング
- ホワイトペーパー
- オウンドメディア
- SNS
- セミナー・ウェビナー
テレマーケティング
テレマーケティングは、電話にて顧客とコミュニケーションを図る手法です。
電話を使用する施策には「テレアポ」がありますが、テレアポは接点を持たない見込み顧客を対象としています。
インサイドセールスにおけるテレマーケティングは、接点のある見込み顧客にヒアリングを行い、課題の把握と解決策を提案して顧客との関係性を構築するのが目的です。
メールマーケティング
メールマーケティングは、購買意欲があまり高くない見込み顧客へのリードナーチャリングに適しています。
電話では直接顧客と会話ができますが、自社商材への関心が低い場合には話を聞いてもらえない恐れがあります。
メールなら電話よりも多くの情報を伝えられるだけでなく、定期的に配信することで中長期的にコミュニケーションを図れるのがメリットです。
ただし、開封してもらえなければ意味がありません。顧客が読みたいと思えるタイトルや、有益な情報を提供するといった工夫が求められます。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、自社商材に関する情報をまとめた資料です。
カタログやパンフレットとは異なり、より専門性の高い情報を顧客に提供することを目的としています。
インサイドセールスにおけるリードナーチャリングでは、顧客が抱える課題に対して専門性の高い知識を元に、最適な解決策を提案できるとアピールする役割があります。
顧客にとって有益な情報と解決策を提案できれば、信頼できる企業と印象付けられるでしょう。
オウンドメディア
オウンドメディアは、自社で運営するメディアのことです。Webサイトやブログ、パンフレットや広報誌などが該当します。
たとえば、自社Webサイトのコンテンツやブログで、顧客にとって有益な情報を発信すれば、資料請求や問い合わせにつながる可能性があります。
SNS
SNSは、情報拡散力に優れているのが特徴です。
SNSで積極的に有益な情報を発信していけば、確度の高い見込み顧客の目に留まることもあります。投稿を見た顧客から、ダイレクトメッセージで問い合わせが来るケースも少なくありません。
潜在層との接点につながる可能性があるので、SNSをきっかけにファン化を促すこともできます。
セミナー・ウェビナー
そもそも、セミナーに参加するのは、自社商材への関心や興味が高い顧客と考えられます。
参加者に直接自社商材のメリットやベネフィットを伝えられるので、顧客がイメージしやすいのも特徴です。
ウェビナーなら、会場に足を運ぶ必要がないので、参加へのハードルが下がります。
ただし、インサイドセールスにおける施策として実施する場合は、顧客にとって有効なテーマを設定する必要があることに留意しましょう。
インサイドセールスでリードナーチャリングを進める手順7ステップ

インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの手順は、以下の7ステップで進めていきます。
- ペルソナを具体的に設定する
- カスタマージャーニーマップを作成する
- 顧客への理解を深めるために仮説を構築する
- リードナーチャリングの施策を決定する
- リストをセグメント分けする
- リード情報の管理ツールを導入する
- 効果測定と改善をする
ステップ1.ペルソナを具体的に設定する
インサイドセールスにおけるペルソナは、自社商材を利用する人物像を設定して顧客の課題やニーズを正しく理解する目的で設定します。
あくまで架空の人物像ですが、具体的に設定することにより顧客が抱える課題への理解が深まり、最適な解決策を提案できるのがメリットです。
BtoCでは個人で設定しますが、BtoBでは企業と担当者でそれぞれペルソナを設定します。
また、設定したペルソナ像は社内で共有して、認識のすり合わせも大切です。
なお、課題やニーズは顧客によって異なるため、複数のペルソナを設定する必要があります。
ステップ2.カスタマージャーニーマップを作成する
次に、顧客が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの行動を見える化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。
以下は、インサイドセールスにおけるリードナーチャリングのフォーマット例です。
| 認知 | 理解 | 比較検討 | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
| 行動 | 課題に気づき解決策を探すことで〇〇(商材)を知る | 〇〇に関する事例や情報を調べる 入手した情報を元に検討する | 企業に問い合わせる | 商談に応じる |
| タッチポイント | 展示会 テレアポ SNS | Webサイト セミナー ウェビナー | 資料請求 問い合わせフォーム | 営業商談 |
| 感情 | 課題を解決したい | 具体的なイメージが湧き興味を持つ | 〇〇が課題解決になると理解し購入を検討する | 具体的な導入に向けて商談に応じる |
横軸にフェーズを、縦軸に顧客の行動やタッチポイントなどを設定します。
項目は必ずしも一律ではありませんが、設定したペルソナに当てはめながら作成すれば、最適なアプローチを見出せるでしょう。
また、顧客の認知から購入までを見える化することで、顧客体験の向上効果が期待できる他にも、青アプローチすべき湯煎順位を明確にできるといったメリットもあります。
ステップ3.顧客への理解を深めるために仮説を構築する
ペルソナを具体的に設定すれば、顧客が抱える課題を理解しやすくなりますが、より理解を深めるには仮説立てが重要です。
ある程度顧客が抱える課題や最適な解決策を立案しても、顧客が想定外の行動を取る可能性は否定できません。
仮説立てをすることで、顧客が想定外の行動を取った場合にも柔軟に対応できます。顧客への理解が深まれば、自ずとすべきことも正しく理解できるでしょう。
ステップ4.リードナーチャリングの施策を決定する
そして、リードナーチャリングの施策を決定します。
- テレアポ
- メールマガジン
- ホワイトペーパー
- セミナー・ウェビナー
- SNS
- オウンドメディア
このようにインサイドセールスにおけるリードナーチャリングの施策は、さまざまであり顧客によって異なります。
顧客への理解を深めて仮説立てをするのは、最適な施策の選定にも役立つからです。
ステップ5.リストをセグメント分けする
次に、リストをセグメント分けして、アプローチの優先順位を決めてください。
見込み顧客といっても、自社商材への興味・関心や購買意欲はそれぞれ異なります。
購買意欲が低い顧客にアプローチしても、成果につながる可能性は低いでしょう。
セグメント分けすることで、購買意欲が高い顧客を絞り込んだ上でアプローチできます。確度の高い見込み顧客なら、成果につながりやすいので生産性の向上にもつながります。
ステップ6.リード情報の管理ツールを導入する
収集した顧客情報から精度の高い分析をするには、多くのデータが必要です。膨大なデータを収集したり、分析したりするには時間と手間もかかります。
そこで、リード情報の管理にツールを活用すれば、作業の自動化が可能です。業務効率がアップすれば、より多くの見込み顧客にアプローチできます。
ステップ7.効果測定と改善をする
インサイドセールスにおけるナーチャリングは、施策を実施したら終わりではありません。継続的に効果測定と改善を繰り返すことも重要です。
- P(Plan)計画
- D(Do)実行
- C(Check)評価
- A(Action)改善
PDCAサイクルを回しながら効果測定と改善を繰り返せば、回数を重ねるごとに精度が向上します。
なお、PDCAサイクルのスパンが長すぎると、課題の発見と改善がスムーズにいきません。目安として1週間~2週間など、可能な限り短いスパンで回すのがおすすめです。
インサイドセールスでリードナーチャリングするときのポイント

では最後に、インサイドセールスでリードナーチャリングをするときのポイントを4つ紹介します。
- 部門間で情報共有の体制を整備する
- 顧客の視点を持って丁寧にヒアリングする
- カスタマージャーニーに沿って最適なタイミングでアプローチする
- 内製化が難しいなら外注する
部門間で情報共有の体制を整備する
インサイドセールスは「分業制」を前提としているため、部門間で情報を共有する体制の整備が必要不可欠です。
情報共有がスムーズに行かなければ、認識のズレが生じて業務の遂行を妨げる恐れがあります。業務がストップすれば、顧客に対して最適なタイミングでアプローチできません。
インサイドセールスに欠かせないツールは、活動ログを残せるので部門間の情報共有にも役立ちます。
さらに、ツールに蓄積されたデータを、トークスクリプトやマニュアルの作成にも活用すれば、応対品質の標準化が可能です。
顧客の視点を持って丁寧にヒアリングする
インサイドセールスにおけるリードナーチャリングでは、顧客の視点で丁寧にヒアリングすることも大切です。
企業視点でヒアリングすると、営業感が出すぎてしまう恐れがあります。強引にアプローチしたとネガティブな印象を与えると、顧客との関係性を構築できません。
常に顧客の視点を持ち、丁寧にヒアリングするように心がけてください。顧客に寄り添い共感する「傾聴力」を身につけることも大切です。
カスタマージャーニーに沿って最適なタイミングでアプローチする
自社商材に興味や関心を持つ購買意欲の高い顧客でも、アプローチのタイミングを間違えると失注する恐れがあります。
タイミングを間違えたばかりに、顧客を不安にすればこれまで築いてきた関係性を損ないかねません。一度失った信頼を取り戻すのは非常に困難です。
カスタマージャーニーマップに沿って、顧客の興味や関心が高まったタイミングでアプローチすれば、成果につながりやすくなるでしょう。
さらに、顧客と中長期的な関係性を構築し続けるには、継続的なフォローアップも欠かせません。
内製化が難しいなら外注する
慢性的な人手不足の課題を抱える企業や、起業して間もないスタートアップ企業ではノウハウ不足により、インサイドセールスの内製化が難しいこともあるでしょう。
内製化が難しい場合は、外注という選択肢があります。
ノウハウを持つプロが対応するので、成約率の向上が期待できます。人手不足の課題を抱える企業も、採用や人材教育にかかるコストを削減できるのは大きなメリットでしょう。
外注コストをかけても、将来的に成約率が上がり売上が伸びれば、企業の成長にもつながります。
インサイドセールスにおけるテレアポ代行ならディグロス

株式会社ディグロスでは、テレアポ代行サービスを提供しています。
アポイントメント獲得を成果点とした成果報酬型なので、初期費用や固定費はかかりません。低リスク・低コストでのご利用が可能です。
お客様のご要望に沿った商談の場をセッティングします。
インサイドセールスにおけるテレアポ代行をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ:インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの精度を高めて成果につなげよう

インサイドセールスにおけるリードナーチャリングは、顧客との関係性を構築しながら、最適なタイミングでのアプローチを実現するために欠かせない施策です。
分業制が前提となるため、社内で情報を共有する体制を整備する必要がありますが、各部門の連携を強化すれば成約率向上考課が期待できます。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、インサイドセールスにおけるリードナーチャリング精度を高めて成果につなげてください。