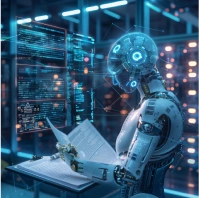営業利益率の平均目安とは?計算方法や高めるコツを紹介

営業利益率は、企業の収益力を評価する重要な指標の一つです。
企業の収益力が低く経営が安定しなければ、企業の存続が危ぶまれる恐れがあります。
「自社の営業利益率を把握したい」
「目指すべき営業利益率の目安が分からない」
利益率にはさまざまな種類があるため、このような悩みや疑問を持つ管理者もいるでしょう。
そこで本記事では、営業利益率の平均目安や計算方法について解説します。高める方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
営業利益率とは企業が本業で稼ぐ利益の割合のこと

営業利益率とは、企業が本業で稼ぐ利益の割合を指します。
売上高(100%)から売上原価と販管費を差し引いた利益の総額であり、高いほど健全な事業であると判断できます。
営業利益率の計算方法

営業利益率の計算方法は、以下の計算式で算出できます。
- 営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
- 売上総利益=売上高−売上原価
- 営業利益=売上総利益−販売費及び一般管理費
「売上原価」は仕入れにかかる費用のことで、「販売費及び一般管理費」は人件費や家賃・水道光熱費などの固定費を指します。
営業利益以外の利益率との違い

それでは、営業利益率とその他の利益率の違いを見ていきましょう。
- 売上総利益率
- 経常利益率
- 税引当期純利益率
- 当期純利益率
売上総利益率
売上総利益率は、売上高から売上原価を差し引いた利益の割合を指します。
粗利とも呼ばれるように、販売費及び一般管理費は含まない大体の利益ですが、商品やサービスの価値を表す指標です。
経常利益率
経常利益率は、通常の営業活動で得た利益の割合を指します。
経常利益率は、下記の計算式で算出できます。
- 営業利益+営業外収益−営業外費用=経常利益
営業外の収益や費用も要素として加えられるため、どの事業にどれくらいの金額がかかっているのか注視してください。
| 営業外収益 | 受取利息 配当金 補助金や助成金 法人税の還付金 |
|---|---|
| 営業外費用 | 社債利息 為替差損 雑損失 |
経常利益率を営業利益と比較すれば、企業全体の収益率を把握できます。
税引当期純利益率
税引当期純利益率とは、本業で発生した経常利益及び特別損益などを考慮した収益の割合を指し、以下の計算式で算出します。
- 経常利益+(特別利益-特別損失)=税引前当期純利益率
企業が1年間に収める税金を支払う前の利益の割合で、利益と損失が反映されています。
なお、税引当期純利益には、法人税や事業税などは含まれていません。
当期純利益率
当期純利益率とは、当期の売上高における最終的な利益はどれくらいか?を示す割合です。企業全体の収益力を判断する指標であり、以下の計算式で算出します。
- 当期純利益÷売上高×100(%)=当期純利益率
なお、当期純利益率がマイナスの場合は、損失を受けたことを意味しています。
営業利益率の平均目安
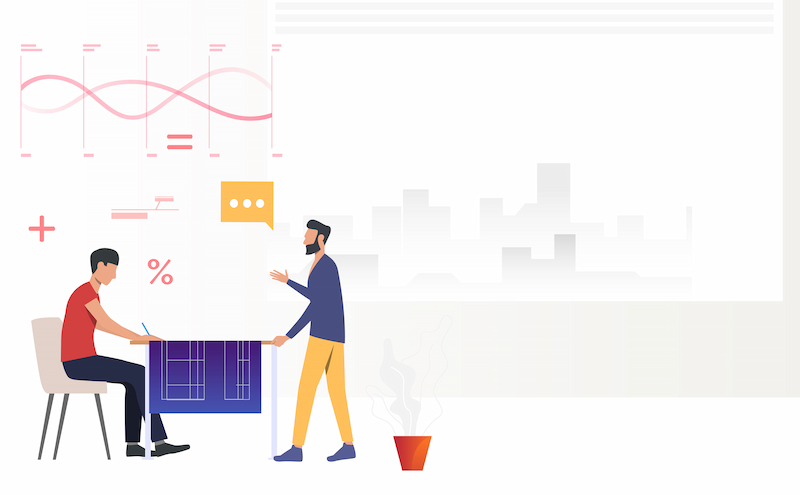
業種による違いはあるものの、営業利益率の平均目安は「0〜5%以下」が標準とされています。
| 営業利益率 | 状態 |
|---|---|
| 0%以下 | 危険 |
| 0%~5%以下 | 標準 |
| 5%~10%以下 | 優良 |
| 10%~15%以下 | 超優良 |
| 15%以上 | 注意 |
営業利益率は高いほど良いとされていますが、15%以上の場合は注意が必要です。
- 人件費が適正ではない(低い)
- 取引先や従業員に負担を強いている
- 顧客サポートが不十分である
営業利益率が高すぎる場合は、このような歪みが生じている可能性が考えられます。
また、マイナスの場合は赤字経営を意味するため、早急に改善しなくてはなりません。
営業利益率が重要視される理由

では次に、営業利益率が重要視される3つの理由を紹介します。
- 企業の健全性を示す指標となる
- 従業員の満足度が向上する
- 競合他社との差別化を図れる
企業の健全性を示す指標となる
営業利益率が「優良」または「超優良」なら、健全な企業であると判断できます。
もし自分が働いている企業、またはこれから働きたいと考えている企業の営業利益率が危険な状態だと、赤字経営で倒産する可能性も否定できません。
健全であれば、経営が安定しているので将来性も期待できるでしょう。
従業員の満足度が向上する
健全な企業は、福利厚生や待遇面も好条件が期待できます。
給料や賞与はもちろんのこと福利構成も充実しているので、従業員やその家族の生活が安定すれば、従業員の満足度が向上するでしょう。
働きやすい環境が整備されていれば、モチベーションもアップして社内全体が活気づくのもメリットです。
競合他社との差別化を図れる
営業利益率が高く経営が安定していれば、新技術・システムの導入や、雇用の拡大なども可能です。
企業全体の組織力を高められれば、競合他社との競争力強化を図れます。
導入コストや採用コストをかけても、業務効率が向上すれば生産性が上がり、結果的に企業にはプラス効果をもたらします。
営業利益率を高める方法

では、営業利益率を高める方法を5つ紹介します。
- 売上を増やす
- 経費を削減する
- 商品やサービスの単価を上げる
- 原価を下げる
- 営業のプロに相談する
売上を増やす
まず、売上を増やせば自ずと営業利益率も増えます。
ただし、売上を増やす目的で高額な広告費用やシステムを導入すれば、必ずしも営業利益率が上がるとは限りません。
売上原価や販売・管理活動にかかるコストをおさえつつ、売上を増やす工夫が必要です。
経費を削減する
経費を削減するのも有効な手段です。
経費には「固定費」「変動費」があります。固定費を無理に減らすと職場環境が悪化する恐れがあるので、バランスを考慮しながら見直してください。
一方で、変動費は消耗品費や販促費であれば、削減しやすいでしょう。
商品やサービスの単価を上げる
商品やサービスの単価を上げれば、販売量を増やさずとも営業利益率を高められます。
ただし、強気の単価設定では新規顧客の獲得が難しくなり、既存顧客離れのリスクも高まるので注意してください。
単価を上げる場合は、付加価値を持たせるとよいでしょう。
原価を下げる
そして、原価を下げるのも有効です。
仕入れ価格を見直す、製造にかかるコストを見直すなどでも、原価を下げられます。
ただし、原価を下げたことで、商品やサービスのクオリティーが下がれば本末転倒です。
クオリティーに影響しない範囲で、原価を下げる工夫を取り入れましょう。
営業のプロに相談する
自社での対応が難しいなら、営業のプロに相談するのも選択肢の一つです。
営業代行サービスを利用すれば、プロのノウハウで営業活動を最適化できます。
外注費用はかかりますが、結果的に営業力が強化されれば売上増加も期待できるでしょう。
営業利益率における注意点

営業利益率における注意点を2つ紹介します。
- 粗利益が高ければ良いわけではない
- 価格設定に注意する
粗利益が高ければ良いわけではない
必ずしも、粗利益が高ければ良いわけではないと理解しましょう。
粗利益が高くても、販売費や管理費が高い場合は損失が増えるリスクがあるからです。
粗利益だけで判断せずに、営業利益率やその他の利益率とのバランスを比較しながら、自社にとっての最善を見極めることが大切です。
価格設定に注意する
そして、価格設定にも注意が必要です。
価格設定では、値入率(販売価格と仕入れ原価の差額に対する利益率)を指標にしますが、原価に値入率をかけないように注意してください。
価格設定は、原価÷(100%-利益率)で算出しましょう。
営業利益率が上がらない時はコンサルティングがおすすめ

営業利益率を高めるための営業強化を図るなら、コンサルティングを検討するのも選択肢の一つです。
株式会社ディグロスでは、業界トップを誇る「セールス×アウトバウンド」の豊富な経験を活かした、セールスコンサルティングサービスを提供しています。
15年以上の経験で培ったノウハウと、3,000社以上の企業を支援した実績があり、戦略策定から実行・評価まで一貫したエンドツーエンドサポートを実現します。
営業利益率を高めたいとお考えの企業様は、電話やメールでご説明しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ:営業利益率を高める取り組みで企業の利益を伸ばそう

営業利益率が高いほど、健全な企業であると評価できます。
0~5%以下が標準とされていますが、営業利益率を高める方法を実践すれば改善できる可能性があります。
自社対応が難しい場合は、営業代行やコンサルティングサービスを活用するのもおすすめです。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、営業利益率を高める取り組みで企業の利益を伸ばしてください。