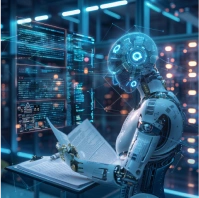営業マニュアル作成ガイド!売れる仕組みを作る項目とテンプレートも

営業マニュアルは、新人スタッフの教育に不可欠であり、組織全体のパフォーマンス向上といった効果も期待できます。
とはいえ、マニュアルを作成しても正しく活用できなければ意味がありません。
そこで本記事では、営業マニュアルの作成で得られるメリットや、記載する項目とテンプレートについて解説します。作成手順や有効な営業マニュアルを作成するコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
営業マニュアルとは?

営業マニュアルとは、人材育成や営業品質の標準化を目的として、営業活動の行動指針をまとめたものです。
具体的には、商談の進め方や顧客対応といった営業活動の流れやマナー、商品知識や営業ノウハウなどを網羅的に記載します。
営業マニュアルを活用すれば、新人教育にかかるコストを削減し、誰もが一定レベルのパフォーマンスを発揮できるようになるため、組織全体の営業力底上げにつながります。
営業マニュアルがないとどうなる?

営業マニュアルがないと、以下のようなリスクが生じます。
- 営業スキルの属人化:トップセールスに仕事が集中してチームのパフォーマンスが低下する
- 営業品質の低下:対応や提案内容にばらつきが生じて顧客からの信頼を失う
- 人材育成の負担が増える:教える人によって内容に差が出るため教育コストが増大する
これらのリスクを放置すれば、チーム全体の営業力が伸び悩み、大きな機会損失につながります。
だからこそ、営業マニュアルの整備は企業の成長に欠かせません。
営業マニュアルを作成する6つのメリット

それでは、営業マニュアルの活用で得られる6つのメリットを紹介します。
- 教育体制の基盤を作れる
- 応対品質を標準化できる
- 業務効率化を図れる
- リードタイムを短縮できる
- 属人化を防げる
- コスト削減につながる
教育体制の基盤を作れる
営業マニュアルの作成により、教育体制の基盤を確立できるのは非常に大きなメリットです。
新人教育では、指導者によって教える内容や質にばらつきが生じがちですが、マニュアルがあれば誰が教えても同じ基準で効率的に指導できます。
さらに、新人教育にかかる時間が短縮されるので、指導者への負担も軽減されるでしょう。
応対品質を標準化できる
そして、応対品質を標準化できる、というメリットもあります。
「営業マニュアルがないとどうなる?」の章でも述べた通り、営業マニュアルがなければヒアリングや提案内容が個々のスキルに依存します。その結果、応対品質にばらつきが生じ、顧客との関係性を構築できなければ成果にはつながりません。
そこで営業マニュアルがあれば、正しい商談の進め方や提案方法が明確化され、チーム全体で一定レベル以上のサービスを提供できるようになります。
応対品質を標準化できれば、見込み顧客を顧客に転換できる可能性を高め、リピーターの確保や新規顧客の紹介など新たなビジネスチャンスにつながります。
業務効率化を図れる
業務量が多く煩雑化しやすい営業職にとって、業務効率化を図れるのも大きなメリットです。
たとえば、作業で悩んだときに、マニュアルがあればスムーズに欲しい情報にアクセスできます。よくある質問と回答をまとめておけば、スタッフ自身で疑問を解決できるようになるでしょう。
このように、無駄な時間を減らしてコア業務に集中できれば、顧客との関係性構築に注力できます。
リードタイムを短縮できる
営業マニュアルでノウハウを共有すれば、担当者のスキルや経験を問わずに、品質を保った提案書や資料を作成できます。
これにより、顧客へのアプローチから成約までのプロセスがスムーズに進み、リードタイムが短縮されればより多くの案件に対応できるでしょう。
結果として、組織全体の売上向上が期待できます。
属人化を防げる
属人化は多くの企業が抱える課題であり、早急な改善が不可欠です。その点、営業マニュアルは属人化を防ぐための有効な手段となります。
個人のスキルに依存しないため、誰でも一定水準の業務をこなせるようになります。
トップセールスのノウハウを共有すれば、組織全体の営業力も底上げされるでしょう。もし途中で担当者が交代しても、スムーズに引き継ぎできます。
コスト削減につながる
営業マニュアルは、さまざまなコスト削減に貢献するのもメリットです。
新人教育では、研修時間を大幅に短縮でき、指導者の負担も軽減できます。
また、営業ノウハウをマニュアル化することで、情報収集や質問にかかる無駄な時間を省けば、生産性の向上につながるでしょう。
結果として、各担当者の生産性が向上し組織全体の営業効率が高まるため、人件費を含めたコストを削減できます。
営業マニュアルに記載する項目とテンプレート

それでは、営業マニュアルに記載する項目と、テンプレートをそれぞれ紹介します。
- はじめに
- 営業方針やビジョン
- 自社商材に関する情報
- 営業の基礎知識や求められるスキル
- 営業プロセス
- 顧客対応
- 顧客管理
- クレーム・緊急時の対応
はじめに
冒頭は、マニュアルの導入部分となる重要な項目です。
マニュアルを作成した背景や目的、使い方などを簡潔に説明します。
なお、顧客情報や機密情報などが含まれるケースでは、情報の取り扱い方やルールも記載しておくとよいでしょう。
テンプレート例
- マニュアルの背景と目的
- マニュアルの対象者
- 使用方法
- 管理方法
改定ルールがあれば末尾に記載しておきましょう。
営業方針やビジョン
営業方針やビジョンの項目では、組織の基本方針や理念、ビジョンなどを可視化してチームで共有します。
テンプレート例
- 会社概要と経営理念
- 営業方針とビジョン
- 営業の役割と目的
- 行動規範
ここでは、チームの方向性を統一するという目的もあります。
自社商材に関する情報
自社商材に関する情報の項目では、営業活動の土台となる「自社商材への理解」を深めるのが目的です。
テンプレート例
- 自社商品やサービス一覧
- 自社商材の強みと付加価値
- ターゲット
営業の基礎知識や求められるスキル
営業の基礎知識や求められるスキルの項目では、営業担当者が把握すべき心構えやスキルを学べます。
テンプレート例
- 営業の心構え
- ビジネスマナー
- ターゲットや業界の基礎知識
- 市場動向やトレンド
- マーケティングの基礎知識
- 電話対応やメールのマナー
- 営業担当者に必要なスキル
- 業務に関連する法律や規律
営業担当者に必要なスキルとして「コミュニケーションスキル」「プレゼンテーションスキル」「スケジュール管理・タスク管理」などをそれぞれ記載します。
営業プロセス
営業プロセスの項目では、フェーズごとに整理しながら、誰が見てもわかるようにまとめます。
テンプレート例
- 業務の全体像(リード獲得~アフターフォローまで)
- 業務手順(各ステップの詳細)
- 社内業務(見積書・資料作成、社内手配フローなど)
上記はあくまでも一例ですが、社内業務ではルーチンワークも記載しておくとよいでしょう。
顧客対応
顧客対応の項目では、顧客と良好な関係性を構築するルールをまとめます。
テンプレート例
- 基本的なマナー(電話・メール・チャット対応など)
- 新規顧客への対応
- 既存顧客への対応
- 商談のトークスクリプト
- 顧客との関係構築
- よく聞かれる質問
トークスクリプトは、アプローチ方法や状況に応じて、複数作成するのもコツです。
また、市場動向や顧客ニーズの変化に合わせて、定期的に内容を見直すことも大切です。
顧客管理
顧客管理の項目では、顧客情報を適切に管理するルールをまとめます。
テンプレート例
- 顧客情報や機密情報管理のルール
- 情報共有のルール
- 引き継ぎフロー
- ツールの使い方
情報共有の項目では、部門間での情報共有の仕方や、報告義務なども記載しておくとよいでしょう。
クレーム・緊急時の対応
営業活動では、予期せぬ事態が発生することも少なくありません。クレーム・緊急時の対応の項目では、予期せぬ事態に遭遇した場合の対処方法を記載します。
テンプレート例
- クレーム対応フロー
- トラブル発生時の対処法
- 報告ルール
- 過去事例と対応策
- 緊急時の連絡先
トラブルやクレームは、顧客によって内容が異なるので、都度更新しながら蓄積してナレッジとして活用しましょう。
営業マニュアルの作り方9ステップ

では次に、営業マニュアルの作成手順を9つのステップに分けて紹介します。
- 目的を明確にする
- マニュアルの利用者を決定する
- マニュアルの内容や取り入れる情報・知識を言語化する
- フォーマットを決定する
- 作成スケジュールを決定する
- 営業マニュアルを作成する
- 本文をまとめる
- 運用する
- 定期的にブラッシュアップする
ステップ1.目的を明確にする
まず「誰がどのような目的で扱うのか」を明確にしてください。なぜなら、対象者によって記載するべき内容が変わるからです。
対象者を絞ることで、本当に必要な情報だけを盛り込んだ実用性の高いマニュアルを作成できます。
ステップ2.マニュアルの利用者を決定する
次に、マニュアルの利用者を決定してください。
マニュアルの内容が利用者に合っていないと、使われずに終わってしまう可能性があります。
- 新人スタッフ向け:業務フローやトークスクリプトなどの基本を網羅
- マネージャー向け:マネジメントや営業戦略などチームのパフォーマンス向上に役立つ内容
このように、利用者を明確にしてから作成すれば、レベルに合った効果的な営業マニュアルを作成できます。
ステップ3.マニュアルの内容や取り入れる情報・知識を言語化する
マニュアルに盛り込む情報や知識は、具体的に言語化することも大切です。
たとえば「営業のコツ」だけでは、漠然としていて具体的なイメージが湧きません。
- 新規顧客を対象としたアプローチ方法
- 商談におけるヒアリング項目
このように、具体的かつ誰が見ても理解できるように記載すれば、マニュアルの信頼性と実用性が高まります。
ステップ4.フォーマットを決定する
次に、フォーマットを決定しましょう。
フォーマットは、対象者に合わせて使い分けるのも有効です。
- 新人社員向けの基礎知識:目次形式でステップごとに項目を分ける
- 中堅社員向けの最新情報:検索機能付きのデジタルフォーマット
フォーマットには明確なルールがないので、対象者に合わせて最適なフォーマットを決めるのもポイントです。
ステップ5.作成スケジュールを決定する
作成スケジュールを決定しないと、期日に間に合わない恐れがあります。
はじめに、完成日を決めて、そこから各ステップのスケジュールを逆算して決めていくとよいでしょう。
- マニュアルに記載する項目を洗い出す
- 情報を言語化する
- 全体を見直し修正する
上記は一例ですが、ステップごとに担当者や目標を明確にすれば、質の高いマニュアルを作成できます。
ステップ6.営業マニュアルを作成する
ここまで準備してきた内容(目的、対象者、フォーマットなど)に基づいて、次に営業マニュアルを作成します。
決定したフォーマットに沿って、具体的に記述することも大切です。
誰が見てもわかるように、「専門用語には解説を入れる」「図やイラストなど視覚的な要素を取り入れる」といった工夫も取り入れるとよいでしょう。
ステップ7.本文をまとめる
次に、本文をまとめながら見直していきます。
文章に誤字や脱字はないか、不自然な表現はないかなどを確認しながら丁寧に校正しましょう。
さらに、フォントのサイズや種類、図やイラストの配置などに統一感をもたせると、読みやすいマニュアルになります。
ステップ8.運用する
マニュアルは作成したら終わりではありません。運用開始後は、現場で活用されているかを確認してください。
また、マニュアルを必要としている対象者に配布されているかも重要です。あらかじめ、対象者と配布範囲を決めておけば、全員に行き渡ります。
なお、オンラインマニュアルを採用する場合は、セキュリティ対策も必要になるでしょう。
ステップ9.定期的にブラッシュアップする
市場動向や顧客ニーズは常に変化するため、マニュアルもそれに合わせて定期的にブラッシュアップする必要があります。
たとえば、新しい商品やサービスがリリースされた場合は、関連する情報の修正や追記が必要です。
さらに、現場からのフィードバックを元に、活用されていない箇所の削除や、わかりづらい表現の修正なども取り入れてください。
有効な営業マニュアルを作成する5つのコツ

では最後に、有効な営業マニュアルを作成する5つのコツを紹介します。
- 利用者に合った内容にする
- わかりやすく具体的に記載する
- デジタルツールを活用する
- 重要な箇所を強調する
- フィードバックをもらい定期的に改善する
利用者に合った内容にする
マニュアルは、内容が利用者に合っていることが重要です。漠然とした内容では、利用者が必要とする情報を提供できません。
作成前には、対象者と目的を明確にして、作成時には利用者を想定しながら進めることで本当に役立つマニュアルを作成できます。
わかりやすく具体的に記載する
誰が読んでもすぐに内容を理解できるようにするには、わかりやすく具体的に記載することも大切です。
「抽象的な表現を使わない」「具体的な言葉や数字で記述する」などを意識しながら作成するとよいでしょう。
また、無駄な情報が多いと、本当に必要な情報が埋もれてしまい利用者に伝わりません。情報を詰め込みすぎないことも重要です。
デジタルツールを活用する
営業マニュアルは、デジタルツールを活用した作成がおすすめです。
GoogleドキュメントやWordで作成して管理をすれば、時間や場所を問わずにマニュアルを確認できます。
また、社内wikiを活用すれば、キーワードから検索から欲しい情報に素早くアクセスできます。
デジタルツールは、内容の修正や更新もしやすく、リアルタイムで反映されるのもメリットです。
重要な箇所を強調する
読み手にとって見やすさを考えたとき、重要な箇所を太字にしたり、文字色を変えたりするのも有効です。
たとえば、トークスクリプトで好感を持たれやすい話し方や、商談時に重要となる確認事項を強調すれば一目でわかります。
長文になる場合は、箇条書きや表を活用すると、視覚的に把握できるので頭に入りやすくなるでしょう。
フィードバックをもらい定期的に改善する
フィードバックは、定期的かつ積極的にもらってください。
「ここがわかりづらい」
「イメージが付きづらい」
現場からのフィードバックに基づきマニュアルを改善していけば、現場ニーズに対応した、より実践的で精度の高いマニュアルに進化します。
これにより、営業活動を強力にサポートするツールとしても活用できます。
まとめ:営業マニュアルを活用して安定した成果を出せる組織を築こう

営業マニュアルは、単なる情報の羅列ではなく、チームの営業力を強化するためのツールです。
利用者と目的を明確化したうえで、わかりやすく具体的に記述することも意識してください。
また、営業マニュアルは作成がゴールではなく、運用開始後の見直しや改善も必要です。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、営業マニュアルを活用して安定した成果を出せる仕組みを構築してください。