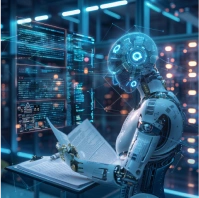SFAを導入する目的と効果とは?機能や選び方も網羅的に解説

営業活動における業務効率の低下や属人化、そして成果に結びつきにくい営業手法を続けると、やがて企業の成長そのものを妨げる要因になりかねません。
そこで、SFA(営業支援システム)を導入すれば、これらの課題は根本から解決できます。
とはいえ、具体的なメリットや、どう活用すればいいかと不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、SFAを導入するメリット・効果や選び方、機能について詳しく解説します。成功させるコツや注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
SFA(営業支援システム)の導入目的

SFA(営業支援システム)を導入する主な目的は、営業活動の課題を解決し、企業の成長を加速させることにあります。
具体的には、以下のような目的で導入されています。
- 生産性の向上で売上を伸ばすため
- 営業活動を一元管理するため
- ナレッジの集約で標準化をするため
以降でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
生産性の向上で売上を伸ばすため
SFAを導入する最も重要な理由は、営業担当者一人ひとりの生産性を高め、チーム全体の売上を最大化することです。
営業職においては、顧客情報の入力や日報作成、案件管理といった煩雑な事務作業が、担当者の時間的な負担を増やしてしまいます。
SFAは、これらの定型業務を効率化することで、商談や顧客との関係構築といったコア業務に注力できるようになります。
結果、より多くの案件をスムーズに進められるようになり、成約率の向上や売上アップにもつながるでしょう。
営業活動を一元管理するため
営業活動の見える化と、情報の一元管理の実現も大きな目的です。
顧客情報や商談の進捗状況、営業担当者の活動履歴などが個別に管理されていると、属人化を招きブラックボックス化する原因となりかねません。
SFAを活用すれば、これらの情報をリアルタイムで一元管理でき、営業管理者はチーム全体の状況を正確に把握できます。
また、個々の案件に対して、適切なアドバイスやサポートが可能になるのもメリットです。
日報の集計や進捗確認に費やしていた時間が削減されるため、営業管理者の業務負担も軽減されるでしょう。
ナレッジの集約で標準化をするため
SFAを使わない場合、営業の成功事例やノウハウは、担当者がそれぞれ個別に管理することになります。ナレッジが共有されなければ、営業活動の標準化は進みません。
この状態では、特定の担当者しか成果を出せない属人化が進み、組織全体の営業力は頭打ちになってしまいます。
そこで、SFAを導入すれば、これらのノウハウはシステム上にデータとして集約・蓄積されます。
個人の経験やノウハウをチーム全体で共有できるようになるため、誰でも安定した成果を出せるような仕組みを構築できます。
SFAでできる主な機能

SFAには、営業活動の各プロセスを効率化し、成果を最大化するためのさまざまな機能が搭載されています。
ここでは、特に重要な6つの主要機能を紹介します。
- 顧客情報管理機能
- 案件管理機能
- 商談管理機能
- 行動管理機能
- 予実管理機能
- 営業担当者の支援機能
顧客情報管理機能
顧客情報管理機能は、顧客の基本情報(企業名・担当者名・連絡先)に加えて、過去の商談履歴や問い合わせ内容などをシステム上で一元的に管理できます。
この機能により、顧客情報を整理して担当者間でスムーズに共有できるため、顧客に合った的確な提案が可能です。
案件管理機能
案件管理機能を活用すれば、現在進行中の商談や案件進捗状況の可視化が可能です。
顧客名や商談のフェーズ・受注確度・想定売上金額などの情報を案件ごとに登録し、チーム内でリアルタイムに共有できます。
この機能により、営業管理者は遅れている案件を素早く把握し、適切なタイミングでアドバイスやサポートができるようになります。
商談管理機能
商談管理機能は、各商談の情報を詳細に記録・管理できます。
商談の履歴や進捗状況が可視化されるため、担当者が複数いる場合でも、情報を共有しスムーズな連携が可能です。
また、過去の商談データを分析すれば、成約に至った要因や失注の理由を客観的に把握できるようになり、今後の営業戦略に活かせます。
行動管理機能
行動管理機能は、営業担当者の日々の活動を記録・管理します。
電話や訪問といった営業活動を時系列で記録し、個人の活動量や進捗状況が可視化されるので、チーム全体の活動状況を把握できます。
蓄積されたデータは、目標達成に向けた進捗の評価や、成果につながった行動パターンの分析などに役立つでしょう。
予実管理機能
予実管理機能は、設定した目標に対して、現在の実績がどうなっているかを可視化・管理する機能です。
案件ごとに目標と実績をリアルタイムで比較できるため、進捗の遅れをすぐに把握し、迅速に軌道修正できます。
蓄積されたデータは、なぜ目標が達成できなかったのかを分析し、今後の営業方針を見直すうえでも役立ちます。
営業担当者の支援機能
SFAには、営業担当者一人ひとりの活動を支援する機能も搭載されています。
たとえば、日報や活動報告をスマートフォンから簡単に入力・作成できる機能は、移動中や外出先でも業務を完結できます。
また、システムに蓄積された顧客や案件の情報を活用すれば、成果につながったノウハウをチーム全体で共有できます。
担当者一人ひとりがスキルアップすれば、組織全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
SFAを導入する6つのメリット・効果

それでは、SFAの導入により得られる6つのメリットと効果を紹介します。
- 営業活動を見える化できる
- 営業活動の業務効率化につながる
- ナレッジやノウハウを蓄積できる
- スムーズに情報共有できる
- データに基づく客観的な意思決定が可能になる
- 適正な評価が可能になる
営業活動を見える化できる
まず、営業活動のあらゆる情報が可視化されることが挙げられます。
担当者ごとの営業活動をリアルタイムで把握できるようになれば、目標達成に向けた課題を早期に発見し、迅速な改善策を講じることが可能です。
また、営業の管理者はチーム全体の情報を一元的に把握できるため、個別の状況に合わせた具体的なフィードバックや支援が可能になります。
営業活動の業務効率化につながる
SFAは、日報作成や顧客情報の入力といったルーチン業務を自動化することで、営業担当者の業務を効率化します。
これにより、営業担当者は商談や顧客との関係構築といったコア業務に、より多くの時間を割けるようになります。
顧客一人ひとりに向き合う時間が増え、きめ細かな対応が可能になれば、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
ナレッジやノウハウを蓄積できる
ナレッジやノウハウを蓄積できるのは、チームにとって大きなメリットです。
これまで個々の担当者が持っていた成功事例やノウハウが、SFAにデータとして集約・共有されれば、新人でもベテランのノウハウを学び、実践できるようになります。
結果として、営業活動の品質が底上げされ、チーム全体の営業力を標準化できれば、教育コストの削減にもつながるでしょう。
スムーズに情報共有できる
社内の情報共有をスムーズにし、組織の透明性を高められるのもメリットです。
これまで、特定の担当者しか把握していなかった顧客情報や案件の進捗状況などを、システム上でリアルタイムに共有すれば、属人化を防げます。
これにより、担当者の不在時や異動・退職時でも、他のメンバーがすぐに状況を把握し対応できるため、チーム全体の連携も強化されるでしょう。
データに基づく客観的な意思決定が可能になる
そして、勘や経験に頼っていたこれまでの意思決定から、データに基づいた客観的な意思決定が可能になるのもメリットです。
SFAに蓄積された営業活動の履歴を分析すれば、成功した要因や失敗した原因を客観的に分析・解明できます。
これにより、個人の経験や直感に依存せず、論理的な根拠に基づいて営業戦略を立案できるでしょう。
適正な評価が可能になる
SFAの導入は、営業担当者の公平かつ適正な評価を実現します。
営業活動の履歴や成果が、データとしてシステム上に記録されるため、上司は個人の努力やプロセスを客観的な根拠に基づいて評価できます。
これにより「誰がどのようなプロセスで成果を出したのか」が明確になり、担当者は自分の努力が正当に評価されていると感じられるでしょう。
その結果、営業担当者のモチベーションがアップすれば、チーム全体の生産性向上につながります。
導入するSFAの選び方

SFAを導入する際は、自社に合った製品を選ぶことが重要です。
ここでは、SFAを選ぶ際におさえておきたい7つのポイントを紹介します。
- 機能で選ぶ
- 使いやすさで選ぶ
- 予算に合わせて選ぶ
- モバイル対応の有無を確認する
- 安全性の高さで選ぶ
- サポート体制の充実度で選ぶ
- ベンダーの販売実績で選ぶ
機能で選ぶ
まず、自社の課題や目的に合った機能が備わっているかを確認しましょう。
必要な機能がなければ、SFAを導入しても課題解決にはつながりません。
たとえば「営業プロセスのボトルネックを特定したい」という課題があるなら、案件管理や予実管理の機能が不可欠です。
また「営業担当者の事務作業を減らしたい」という目的であれば、日報作成や顧客情報入力を簡略化できる機能が求められます。
使いやすさで選ぶ
誰でも直感的に操作できる使いやすさも重要なポイントです。
どんなに高機能なSFAでも、現場の営業担当者が使いづらいと感じれば、結局使われなくなってしまうリスクがあります。
導入前に無料トライアルを利用するなどして、実際に操作性を確認しましょう。チームメンバーの誰もが、ストレスなく使い続けられることが大切です。
予算に合わせて選ぶ
SFAの導入費用は、製品によって大きく異なります。
初期費用・月額利用料・サポート費用など、さまざまなコストが発生するため、自社の予算に合った製品を選ぶことが重要です。
特に月額利用料は、利用人数に応じて変動する場合が多いため、チームの規模や今後の人員計画も考慮して検討しましょう。
モバイル対応の有無を確認する
近年では、外出先や移動中に、スマートフォンやタブレットを使って業務を行うことが増えています。そのため、SFAがモバイル対応しているかを必ず確認しましょう。
モバイルに対応していれば、顧客との商談直後にスマートフォンから活動履歴を入力したり、外出先からでも案件の進捗を確認したりできます。
また、PC版とモバイル版で利用できる機能に差がないかも確認したい点です。
たとえば、PC版でしか複雑なデータ分析や詳細なレポート作成ができない場合、外出先で業務が完結できず、非効率になってしまいます。
業務効率を重視するなら、PC版とほぼ同等の機能が使えるかをしっかりチェックしましょう。
安全性の高さで選ぶ
SFAには、顧客の個人情報や企業の機密情報など、重要なデータが数多く含まれるため、安全性の高さは非常に重要です。
安全性の高さを確認する際には、以下の点を確認しましょう。
- データが暗号化されているか
- 不正アクセスを防ぐ機能があるか
- 過去に情報漏えいなどのトラブルがなかったか
- アクセス権限を細かく設定できるか
このように安全性の高い製品を選べば、情報漏洩のリスクを減らし、安心して営業活動に集中できる環境を構築できます。
サポート体制の充実度で選ぶ
新しいシステムを使いこなせるようになるまでには、さまざまな疑問やトラブルが発生します。そのため、充実したサポート体制があるかどうかも重要な選定基準の一つです。
導入時のサポートはもちろん、トラブル発生時に迅速に対応してくれるか、疑問点にすぐに回答してくれるかなどを確認しましょう。
また、システムの不具合など、緊急性の高いトラブルが起きた時に、すぐ対応できなければ大きな損失につながる恐れがあります。
「24時間365日対応してくれる窓口があるか」も確認しておくとよいでしょう。
ベンダーの販売実績で選ぶ
これまでにどれだけの企業に導入されているか、どのような規模や業種の企業に実績があるかなど、ベンダーの販売実績を確認しましょう。
実績が乏しいベンダーの場合、ノウハウが十分でなく、導入後のサポートが不十分になるリスクがあるからです。
実績が豊富なベンダーは、多様な企業の課題解決に取り組んできた経験があるため、自社の業界や規模に合わせた実践的なノウハウを提供してもらえます。
SFAの導入手順7ステップ

SFAの導入を成功させるためには、事前にしっかりとした計画を立てることが重要です。
ここでは、具体的な導入手順を7つのステップに分けて解説します。
- プロジェクトチームを立ち上げる
- 導入目的を確認・整理する
- 導入要件を検討する
- 目的に合うSFAを選定する
- 運用に必要な準備をする
- 運用を開始する
- 運用を定着させる
ステップ1.プロジェクトチームを編成する
まず、プロジェクトチームを立ち上げます。
プロジェクトチームには、営業部門だけでなく、情報システム部門・マーケティング部門・経営層など、各部門からメンバーを選出しましょう。
これにより、それぞれの視点から意見を出し合うことができ、全社的な課題を洗い出し、最適なSFA選定や導入後のスムーズな運用につなげられます。
なお、現場の意見を反映させるために、実際にSFAを利用する営業担当者を必ずチームに加えることが重要です。
ステップ2.導入目的を確認・整理する
次に「なぜSFAが必要なのか」その目的を明確にします。
目的が曖昧なまま導入を進めると、どの機能を使えばいいか分からなくなり、結局使いこなせずに終わるリスクがあるからです。
たとえば、目的別に必要な機能は以下のようになります。
- 業務効率化:日報作成・顧客情報入力などを自動化する機能
- 営業戦略の立案:予実管理・案件管理などデータ分析に役立つ機能
- 顧客満足度の向上:顧客情報を一元管理できる機能
SFAの導入前には、プロジェクトチーム内で意見を共有し、SFA導入によって何を実現したいのかを確認・整理しましょう。
ステップ3.導入要件を検討する
導入目的を明確にしたら、次は「どのようなSFAであれば目的を達成できるか」という導入要件を検討します。
- 予算内に収めること
- モバイル対応が必須
- 既存システムから顧客データを移行できること
上記は一例ですが、このステップで要件をしっかりと固めることで、後のSFA選定がスムーズに進み、自社に最適な製品を見つけられるようになります。
ステップ4.目的に合うSFAを選定する
洗い出した導入要件を元に、複数の製品を比較検討して目的に合うSFAを選定します。
SFAの公式サイトから資料を請求したり、無料トライアルを利用したりして、機能・使いやすさ・コスト・サポート体制などを細かくチェックしましょう。
また、実際にSFAを利用している企業のレビューサイトなども参考にすると、導入後のイメージがつきやすくなります。
ステップ5.運用に必要な準備をする
SFAを選定したら、次は運用に必要な準備をします。
必要な準備は主に、メンバー教育とデータの準備です。
| メンバー教育 | マニュアルの作成実際の操作を交えた研修 |
|---|---|
| データの準備 | 別のツールで管理していた場合はデータを移行する新規で導入する場合はデータを入力する |
なお、データを準備する際は、重複や不備がないように、チーム内でルールを統一しておくとよいでしょう。
ステップ6.運用を開始する
ここまでの準備を整えたら、SFAの運用を開始します。
運用開始後は、目標達成に向けた行動計画を立て、それをチーム全体で共有しましょう。
また、日々の入力や活用のルールをチーム内で再度確認しておくと、誰もが迷わずに使える状態を維持できます。
ステップ7.運用を定着させる
SFAを導入しても、使い続けられなければ意味がありません。運用開始後は、システムを使いこなせるよう促し、現場に定着させることが重要です。
たとえば、導入後も定期的にミーティングを開き、SFAの活用状況を共有しましょう。そこで出た意見を元に改善策を検討すれば、現場の負担が減り運用が定着しやすくなります。
このように、SFAは導入して終わりではありません。活用状況を確認しながら改善を続けていくと、SFAの効果を最大化できます。
SFAの導入を成功させる5つのコツ

では次に、SFAの導入を成功させ、成果を最大化するためのコツを紹介します。
- 目的を明確にする
- 導入目的を周知して社内からの理解を得る
- 費用対効果を確認する
- 使いやすいツールを選ぶ
- 導入後は検証と改善を繰り返す
目的を明確にする
目的が曖昧なままだと、導入したSFAが社内に浸透せず、導入しても活用されない恐れがあります。SFAはあくまで手段であり、導入自体がゴールではありません。
そこで下記のように、目的を明確にしてチームで共有してください。
- ルーチン業務を効率化して残業を減らす
- 顧客情報を共有してチーム全体で売上目標を達成する
結果、チーム全員がSFAを活用する重要性を理解して利用が定着し、SFAの導入効果を最大限に引き出せるでしょう。
導入目的を周知して社内からの理解を得る
現場の社員からの理解と協力は、SFAの導入を成功させるうえで非常に重要です。
SFAの導入によって、これまでやり慣れた営業スタイルや、業務フローを変えることになります。そのため、導入自体にネガティブな感情を抱いてしまうと、現場に定着しません。
導入の目的やメリットを丁寧に周知し、社員の疑問や不安を解消しましょう。社内の理解を得られれば、導入後の利用がスムーズになりSFAの定着率向上にもつながります。
費用対効果を確認する
費用対効果は、しっかりと確認してください。
費用対効果が不透明なまま導入を進めてしまうと、期待したほどの効果が得られず、コストに見合う成果が出ない恐れがあります。
SFAの導入には、以下の費用がかかります。
- 導入費用
- 月額利用料
- 運用・保守費用
- オプション費用など
これらの費用をトータルで把握し、SFA導入によって得られる成果と比較検討しましょう。
使いやすいツールを選ぶ
どんなに高性能なSFAを導入しても、操作が複雑で入力に手間がかかるようでは、現場に定着しません。
重要なのは、現場の担当者にとって使いやすいツールを選ぶことです。
入力画面が見やすく直感的な操作ができるか、モバイルでの利用は快適かなど、利用者の視点でしっかり確認しましょう。
無料トライアルなどを利用して、実際に担当者が操作してみるのもおすすめです。
導入後は検証と改善を繰り返す
導入後にPDCAサイクルを回し、継続的に検証と改善を繰り返すことも重要です。
- Plan(計画):具体的な目標を立てる
- Do(実行):立てた目標を元に運用する
- Check(評価):蓄積されたデータを分析し課題があるかを検証する
- Action(改善):課題を元に改善策を策定・実行する
このサイクルを回すことで、SFAの運用方法や活用方法が徐々に最適化され、効果の確実性が高まります。
SFAを導入する際の注意点

では最後に、SFAを導入する前に確認しておきたい4つの注意点を紹介します。
- 導入コストが高くなる場合がある
- 入力作業の負担が大きくなる場合がある
- SFAの導入が目的ではないことを理解する
- 既存システムやツールとの互換性を確認する
導入コストが高くなる場合がある
製品によっては、導入コストが高くなる場合があることに注意が必要です。
SFAには、無料で利用できるツールや、有料プランでも低価格から試せるものが多く存在します。
しかし、無料プランでは使える機能が限られていたり、ユーザー数が増えると高額になったりするケースも少なくありません。
もしSFAの導入に不安があるなら、まずは無料ツールや無料トライアルから始めることをおすすめします。
なお、こちらの記事では、無料で始められるSFAツールについて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
SFA無料ツールのおすすめ11選!無料と有料との違いを詳しく解説
入力作業の負担が大きくなる場合がある
これまでの営業活動で蓄積してきた情報をすべてSFAに入力しようとすると、膨大な作業量になり、担当者に大きな負担をかける場合があるので注意が必要です。
また、入力ルールが複雑すぎると現場が面倒に感じ、入力が滞ってしまう恐れがあります。
SFAをスムーズに定着させるには、最初からすべての機能を完璧に使いこなそうとするのではなく、スモールから始めるのがおすすめです。
まずは、日報作成や顧客情報の入力など、最も必要とする機能から使い始めるとよいでしょう。
SFAの導入が目的ではないことを理解する
SFAはあくまで、営業活動を効率化したり、売上を向上させたりするための「手段」です。
導入した時点で満足してしまうと、その後の活用が進まず、期待した効果を得られません。
導入後は、定期的にデータの入力状況や利用状況をチェックし、課題があれば改善策を検討するといった、継続的な取り組みが不可欠です。
既存システムやツールとの互換性を確認する
既存システムやツールとの互換性を確認することも重要です。
互換性がない場合、それぞれのシステムに手作業でデータを入力する必要が生じ、業務効率が低下したり、入力ミスが増えたりする恐れがあります。
既存のシステムとスムーズに連携できるSFAなら、データの二重入力を防ぎ、業務効率の向上にもつながるでしょう。
まとめ:SFAの導入で営業課題を解決してチーム力を強化しよう

SFAは、営業活動におけるさまざまな課題を解決し、チームの生産性を向上させるツールです。
SFA導入を成功させるには、目的の明確化から運用・定着まで、計画的に進めることが欠かせません。
本記事で紹介した情報を参考に、SFAの導入で営業課題を解決して、チーム力を強化しましょう。