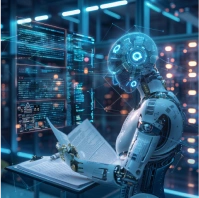商談数を増やすには?9つの方法と8つのステップを解説

「商談数を増やすにはどうしたらいいかわからない……」
このような悩みを抱えている営業担当者も多いのではないでしょうか。
商談数を増やすための施策に注力しても、質の低い商談ばかりでは、最終的な成果にはつながりません。
とはいえ、どのように商談数を増やせばよいかわからず、悩むこともあるでしょう。
そこで本記事では、商談数を増やすにはどうすれば良いのかに焦点を当て、9つの方法と8つのステップを紹介します。
商談数を増やせない原因や、改善すべきポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
商談数を増やせない5つの原因

それでは、商談数を増やせない5つの原因を紹介します。
- ターゲティング精度が低い
- 新規リードを獲得できていない
- ヒアリングや提案内容の質が低い
- 関連部署と有効商談の定義を統一できていない
- アプローチ方法が限定されている
ターゲティング精度が低い
ターゲティング精度が低いと、自社の商品やサービスを必要としない顧客にアプローチしてしまうため、成約につながりにくい質の低い商談ばかりが増えてしまいます。
その結果、商談にはつながっても、成約の見込みが低いため成果にはつながりません。
また、ターゲットが定まっていない状態では、効果的なアプローチ方法もわからず、アプローチすべき顧客を探すのに時間や労力がかかってしまうため、業務効率の低下も招きます。
新規リードを獲得できていない
そもそも、商談数を増やすには、商談のきっかけとなる新規のリード獲得が欠かせません。
新規のリードを継続的に獲得できなければ、既存の見込み顧客に依存することになり、商談のパイプラインが枯渇します。
結果としてどれだけ営業活動を効率化しても、商談数自体を増やすのは困難です。
ヒアリングや提案内容の質が低い
どれだけ商談機会を増やしても、ヒアリングや提案の質が低ければ、成約にはつながりません。
というのも、ヒアリングの質が低いと、顧客の抱える本質的な課題や潜在的なニーズを把握できず、顧客に響く提案ができないからです。
このような状態では、顧客に「うちの課題を理解していない」「商品やサービスを売りつけている」と思われてしまい、商談が進まなくなってしまいます。
関連部署と有効商談の定義を統一できていない
商談数を増やすには、営業部門とマーケティング部門、インサイドセールス部門との連携が欠かせません。
しかし、部署間で有効商談の定義が統一されていないと、以下のような問題が生じます。
- マーケティング部門:見込み確度の低いリードを大量に獲得してしまう
- インサイドセールス部門:質の低いリードを営業部門に引き継いでしまう
- 営業部門:商談の質が下がり成約につながらない
このように、関連部署と有効商談の定義を統一できていないと、組織全体の成果が低下してしまいます。
アプローチ方法が限定されている
アプローチ方法が限定されると、潜在顧客に自社の存在を知らせる機会を逃してしまいます。その結果、見込み客からの問い合わせや、商談につながる機会を失います。
たとえば、Web広告だけにこだわってしまうと、Web広告を閲覧しない層には情報が届きません。獲得できるリードが特定の層に偏れば、商談数を増やすのが難しくなってしまいます。
有効な商談化率の平均

商談化率の平均は、商材や単価によって異なるものの、一般的には30%が目安とされています。
商談化率は「商談化数÷有効なアプローチ件数」の計算式で算出できますが、業界によっても異なることに留意しましょう。
以下に業界別の商談化率の平均をまとめました。
| 業界 | 商談化率 |
|---|---|
| IT業界 | 30~40% |
| サービス業 | 25~35% |
| 金融業 | 25~35% |
| 製造業 | 20~30% |
| 小売業 | 15~25% |
| 不動産業 | 10~20% |
このように、業界によって異なるので、平均値はあくまでも目安の指標として捉えることが大切です。
有効商談数を増やすために改善すべきポイント

では次に、有効商談数を増やすために改善すべきポイントを5つ紹介します。
- アプローチするターゲットを見直す
- 顧客一人ひとりに的確な解決策を提案する
- アプローチ期間を見直す
- 決裁者との信頼関係を構築する
- 商談後も継続的にフォローアップする
アプローチするターゲットを見直す
まず、アプローチするターゲットを、以下の3つの視点から見直してみてください。
- 理想的なペルソナを設定する
- 営業リストを精査する
- 営業リストに優先順位をつける
ペルソナを設定する際には、自社の商品やサービスへの理解を深めたうえで、どのような課題を解決できるのかを把握することが重要です。それを踏まえて、より具体的なペルソナを設定してください。
設定したペルソナを元に、営業リストを精査しましょう。というのも、営業リストには、ペルソナに合致しないターゲットも含まれるからです。
営業リストを精査することで、見込み確度の高いターゲットにアプローチできるようになります。
さらに、購買意欲が高く成約につながりやすいリードに優先順位をつければ、業務効率と成約率の向上が見込めます。
顧客一人ひとりに的確な解決策を提案する
顧客の課題は、一つとして同じではありません。だからこそ、顧客一人ひとりに寄り添い、的確な解決策を提案することが不可欠です。
異なる課題に同じ解決策を提示しても、顧客の心には響かないでしょう。
そのためにも、ヒアリングを通じて顧客の状況を深く理解し、課題を解決するための最適な手段として自社サービスを提案する必要があります。
顧客の課題に寄り添い、課題解決に役立つ提案をすれば、信頼関係が構築され成約率の向上につながります。
アプローチ期間を見直す
顧客の状況や検討段階によって、最適なアプローチ期間は異なります。
たとえば、BtoBビジネスでは、導入までに数ヶ月から1年以上かかることが珍しくありません。このようなケースでは、継続的なアプローチは不可欠です。
しかし、時間をかけすぎて購買意欲が低下してしまうと、成約にはつながりにくくなります。
商談数を増やすには、見込み客の検討期間に合わせて最適なタイミングでアプローチすることが大切です。
決裁者との信頼関係を構築する
どれだけ商談機会を増やしても、最終的に成約に至らなければ意味がありません。そして、商談を成約に導くためには、最終的な意思決定者である決裁者の承認が必要です。
担当者との間で話がスムーズに進んでも、決裁者に承認されなければ商談はそこで止まってしまいます。
決裁者に納得してもらうためにも、導入する商品やサービスが、顧客の経営課題を解決し投資に見合うことを明確に伝える必要があります。
具体的な数値を交えた成功事例や、メリットの先にあるベネフィットなども伝えながら、決裁者の視点に立った提案を意識しましょう。
その結果、決裁者との信頼関係を構築できれば、成約につながりやすくなります。
商談後も継続的にフォローアップする
多くの顧客は、商談後すぐに意思決定をするとは限りません。情報収集や社内稟議など、検討には時間がかかることも少なくないからです。
スムーズに商談が進んでも、その後のフォローアップを怠ると、顧客の購買意欲が低下したり、競合他社に顧客を奪われたりする恐れがあります。
商談後も、顧客の検討状況に合わせて必要な情報を提供し、顧客の興味関心を引き続き維持できるように、継続的なフォローアップを心がけましょう。
- 商談後に要約や導入事例を送付する
- 関連資料を送付する
- 無料トライアルの案内をする
上記は一例ですが、このように商談後も継続的にフォローアップすれば、顧客からの信頼を獲得でき成約につながりやすくなります。
有効商談数を増やす9つの方法・コツ

ここでは、有効商談数を増やすための具体的な方法を9つ紹介します。
- 見込み顧客の母数を増やす
- 精度の高い営業リストを作成する
- ABMを導入する
- リードナーチャリングに力を入れる
- 部門間の連携を強化する
- ツールを活用する
- 組織・個人の営業力を強化する
- 情報共有体制を整備する
- OMOでマルチチャネルに対応する
以降でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
見込み顧客の母数を増やす
そもそも、アプローチする見込み顧客がいなければ、商談数を増やせません。まず、見込み顧客の母数を増やしましょう。
見込み顧客の母数を増やす具体的な方法には、以下のものが挙げられます。
- テレアポ:電話で直接アプローチして商談の機会を創出する
- Web広告:ターゲット層に合わせたWeb広告を配信して見込み顧客を獲得する
- オウンドメディアの活用:ホームページやブログで見込み顧客に有益な情報を発信する
- SNS運用:積極的に情報を発信して潜在顧客との接点を増やす
上記はあくまでも一例ですが、これらの方法を組み合わせて実行すれば、新たな見込み客を継続的に獲得でき、商談の機会を創出できます。
精度の高い営業リストを作成する
有効商談数を増やすためには、精度の高い営業リストを作成することも大切です。
以下のポイントを意識しながら、営業リストを精査してみてください。
- 業界や業種を絞る
- 年収帯で絞る
- 過去の成約実績を基に見込みの高い顧客を選定する
- 役職や決裁権限の有無を考慮する
まず、過去の成功事例を参考にしながら、自社商品やサービスが効果を発揮できる業界や業種・年収帯を特定し、ターゲットを絞り込みましょう。
次に、既存顧客のデータを分析して、成約につながりやすい共通点を洗い出してください。共通点に基づき見込み確度の高い選定すれば、営業リストの質が高まります。
そして、成約までスムーズに進めるには、最終的な意思決定者である決裁者へのアプローチが欠かせません。営業リストには、役職や決裁権限の有無なども記載しておくとよいでしょう。
ABMを導入する
有効商談数を増やすには、ABM(Account Based Marketing)の導入も有効です。
ABMとは、見込み客ではなく、成約確度の高い特定の企業に絞って集中的にアプローチするマーケティング手法であり、以下のメリットがあります。
- あらかじめ選定した質の高いターゲットに集中できる
- ターゲット企業に特化したパーソナライズな提案が可能になる
- 顧客の課題に深く入り込んだ提案ができる
ABMを活用すれば効果的にアプローチできるようになり、成約率や顧客単価の向上はもちろん、有効商談数も増やせるでしょう。
リードナーチャリングに力を入れる
リードを獲得した段階では、購買意欲が低い人も多くいます。
しかし、将来的に顧客になる可能性があるため、リードナーチャリングで購買意欲を高めることが重要です。
特にBtoB営業では、意思決定に複数の人物がかかわるため、購買プロセスが長期的になる傾向があります。
そこで、リードナーチャリングに力を入れ、顧客との関係性を深めながら検討度合いを早めることで、有効商談数を増やすことにつながります。
部門間の連携を強化する
各部門が個別で活動する体制では、営業効率の低下を招きかねません。有効商談数を増やすためには、部門間の連携強化が不可欠です。
たとえば、部門間で顧客情報を一元管理し、リアルタイムで共有する仕組みを構築しましょう。
これにより、顧客の状況に合わせた適切なアプローチが可能になり、組織全体で質の高い商談機会を創出できるようになります。
ツールを活用する
ツールを活用すれば、リアルタイムでの情報共有が可能になり、部門間の連携強化にも役立ちます。
また、情報を一元管理できるため、個人のスキルに依存しがちな営業活動を可視化でき、営業の属人化を防げるのもメリットです。
- SFA(営業支援システム):営業活動の進捗状況や商談内容を可視化する
- CRM(顧客関係管理):顧客への理解が深まり最適な提案ができる
このように、ツールを活用すれば組織全体の生産性が高まり、結果として有効商談数の増加につながります。
組織・個人の営業力を強化する
どれだけ優れた営業リストやツールがあっても、それを活用する営業担当者自身のスキルが不足していては、有効商談数を増やせません。
成果を出すには、勉強会や研修などで、組織・個人の営業力を強化する取り組みが必要です。
また、成功事例・の共有やOJT(On the Job Training)を通して実践的にスキルを習得する方法もあります。
組織・個人の営業力を強化すれば商談の質が向上し、その結果、有効商談数の増加にもつながるでしょう。
情報共有体制を整備する
営業の属人化が進むと、商談の質にばらつきが生じたり、担当者が不在の際に顧客対応が遅れたりする恐れがあります。
有効商談数を増やすには、営業担当者が持つ顧客情報や商談内容を、組織全体で共有することが不可欠です。
そこで、情報共有体制を整備すれば、成功事例やノウハウを組織全体で共有できるようになります。
また、顧客情報や進捗状況が可視化され、営業活動の効率も向上します。
このように、組織全体で情報を共有すれば営業の質が高まり、結果として有効商談数の増加につながるでしょう。
OMOでマルチチャネルに対応する
近年、インターネットの普及やデジタル技術の進化に伴い、顧客が情報を得るチャネルも多様化しています。
有効商談数を増やすには、こうした顧客行動の変化に対して、OMO(Online Merges with Offline)でマルチチャネルに対応することが重要です。
複数のチャネルを持っていても、それぞれが独立していると顧客体験は分断されてしまい、商談機会を逃すことにもつながりかねません。
OMOとは、オンラインとオフラインを融合させ、顧客に一貫した購買体験を提供するマーケティング戦略のことです。
具体的には、公式サイトで自社商材を認知した顧客が、SNSで情報を収集し、最終的に実店舗で購入に至るという流れで購買活動を進めます。
OMOの導入は、顧客がどのチャネルでもスムーズに情報を収集できるため、顧客満足度の向上につながります。その結果、商談の確度が高まれば、有効商談数の増加が見込まれるでしょう。
商談数を増やす手順8ステップ

では最後に、商談数を増やす手順を8つのステップに分けて紹介します。
- 見込み顧客を獲得する
- 見込み顧客への理解を深める
- 営業資料を作成・共有する
- 商談アポイントを獲得する
- ヒアリングで課題とニーズを把握する
- 課題に合わせて解決策を提案する
- 社内稟議をサポートする
- クロージング
ステップ1.見込み顧客を獲得する
まず、アプローチする見込み顧客の母数を増やしましょう。
テレアポや展示会などのオフラインチャネルだけでなく、Web広告やSNSなどのオンラインチャネルを併用しながら、顧客の状況に合わせて最適な施策を展開することが大切です。
見込み顧客の母数が増えれば、商談につながる機会も自然と増加します。
ステップ2.見込み顧客への理解を深める
次は、課題やニーズ・検討状況を正確に把握するため、まずはできるだけ多くの情報を集めて分析し、課題を掘り下げましょう。
そして、既存顧客のデータから成功事例や失注理由を分析して、有効な商談につなげるための共通点やパターンを洗い出しておきます。
このように、見込み顧客への理解を深めておけば、一人ひとりに合わせて最適な提案を準備できます。ナーチャリング精度を高めるためにも、重要な要素です。
ステップ3.営業資料を作成・共有する
営業資料は、相手の課題や状況に合わせてパーソナライズされていることが重要です。
画一的な資料を使い回すと、顧客が「自社に合っていない」と感じ、不信感を与える可能性があります。信頼されずに商談がストップしてしまえば、成約にはつながりません。
そこで、相手の企業情報や課題を踏まえて資料をカスタマイズすれば、顧客は「自社のために準備してくれた」と感じ信頼感が高まります。
加えて、作成した営業資料は、社内で共有しましょう。情報を一元管理すれば、誰でも最新の資料にアクセスでき、どのような資料が成約につながったのかを共有できます。
ステップ4.商談アポイントを獲得する
ここまで準備したことを活かして、次は商談アポイントの獲得に進みます。
アプローチの方法は、テレアポ・メール・問い合わせフォームなどがありますが、いずれの場合も顧客にメリットを明確に伝えることが不可欠です。
たとえば、テレアポはお互いの顔は見えませんが、明るくハキハキと話せば好印象を与えられます。
「〇〇の課題をお持ちではありませんか?」
「貴社の業務効率を〇〇%改善できる可能性があります」
このように課題に対して、具体的にメリットを伝えれば興味を持ってもらいやすくなります。
また、アポイントを打診する際は、顧客の状況に合わせて複数の候補日を提示するなど、相手の負担を減らす配慮をすることも大切です。
ステップ5.ヒアリングで課題とニーズを把握する
初回の商談では、いきなり自社商材を売り込むのではなく、ヒアリングで課題とニーズを把握することを意識しましょう。
- 課題と背景にある理由を深く掘り下げる
- 潜在的なニーズを引き出すために多角的な質問をする
- 決裁権を持つ人物を確認する
上記はあくまでも一例ですが、ヒアリングで課題やニーズを深堀りして、顧客一人ひとりに合わせた最適な解決策を導き出すことが大切です。
ステップ6.課題に合わせて解決策を提案する
ヒアリングで洗い出した課題に合わせて、最適な解決策を提案しましょう。
ここで重要なのは「常に顧客の視点に立つこと」そして「自社商材でどのようなソリューションを提供できるのか」を意識することです。
たとえば、コストの増大という課題を抱えている場合は「当社のソリューションを導入することで、人件費を〇〇%削減できます」のように具体的なメリットを伝えます。
提案に説得力を持たせるなら、導入事例やデータを活用するとよいでしょう。
加えて、導入費用・導入期間・サポート体制など、顧客が抱える不安要素を先回りして解消しておくことも有効です。
ステップ7.社内稟議をサポートする
商談を進め顧客が自社サービスに興味を示したら、顧客の社内稟議をサポートしましょう。
特に、意思決定までに複数の人物がかかわるBtoBビジネスでは、商談相手だけでなく決裁者や関係部署にもメリットを伝える必要があります。
- 決裁者向けの資料を用意しておく
- 稟議書を提供してスムーズな申請をサポートする
- 懸念事項を洗い出し回答を準備しておく
上記はあくまでも一例ですが、このように社内稟議をサポートすれば、購入までのハードルが下がり商談を成約につなげやすくなります。
ステップ8.クロージング
クロージングは、単に契約を結ぶためのものではありません。顧客との信頼関係を築き、最終的な決断を後押しするための重要なプロセスです。
具体的には、ここでもう一度顧客の不安を払拭するために、購入後の成功イメージを明確に伝えましょう。
また、割引キャンペーンがある場合は「今すぐ決める」という顧客の決断を後押しできます。
いずれにせよ、顧客の意思決定をサポートする姿勢が大切です。
まとめ:商談数を増やすには必要な手法と手順・ナレッジの共有が大切

商談数を増やすためには、闇雲にアプローチするのではなく、必要な手法と手順を理解して実行することが重要です。
もし商談数を増やせない場合は、顧客獲得からクロージングまでの各ステップを振り返り、どこに課題があるのかを見つけ出してください。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、ノウハウや顧客情報を組織全体で共有できる体制を整備して、有効商談数を増やしていきましょう。